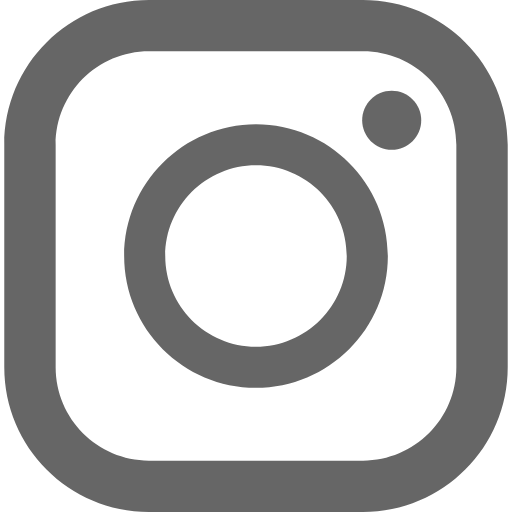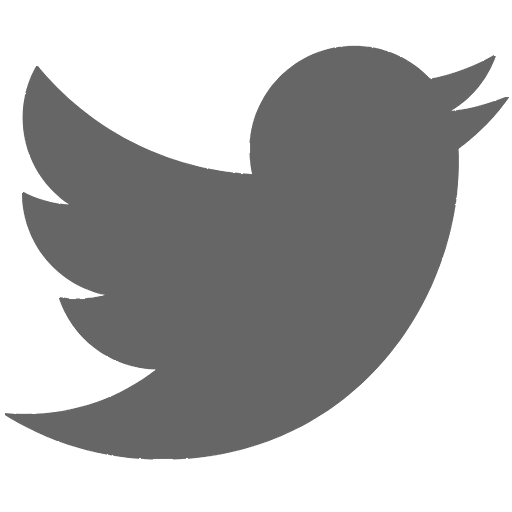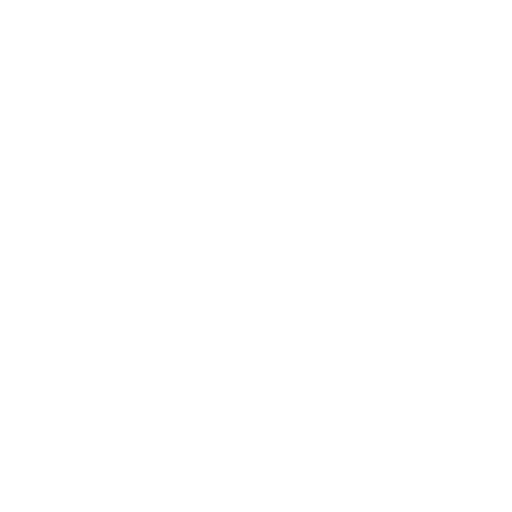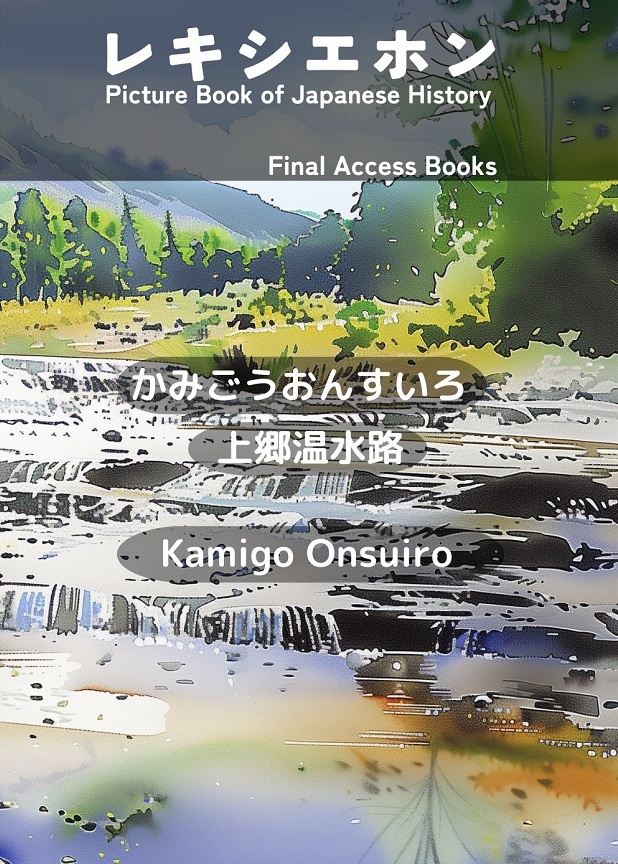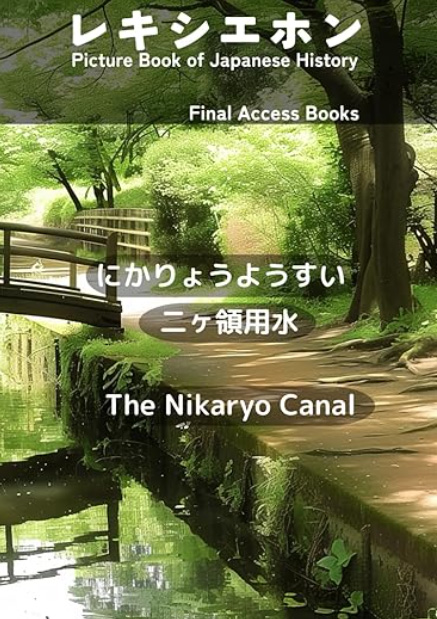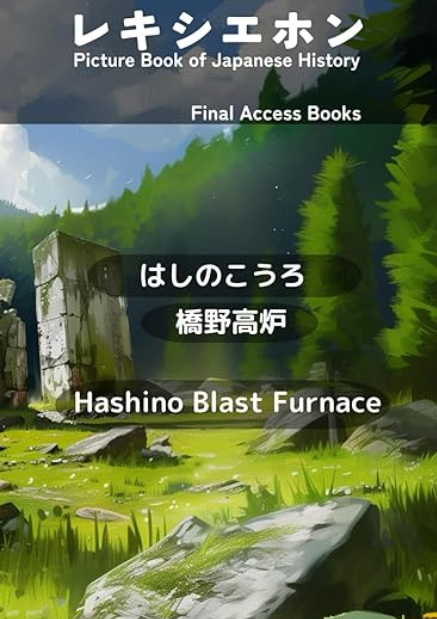観瀾亭
- 文化・教育施設
観瀾亭は宮城県松島町に位置し、その起源は1593年にまでさかのぼります。当初は豊臣秀吉が京都・伏見桃山城に建てた茶室であり、伊達政宗がこれを拝領しました。その後、江戸時代初期に政宗が江戸品川の仙台藩邸へ移築し、さらに二代藩主・伊達忠宗の命により、一木一石も変えず船で現在の松島・月見崎へと移されました。この地は日本三景の一つ松島湾に面し、景勝地として知られています。
観瀾亭は歴代藩主や側室の納涼・観月の宿泊所、また幕府巡見使など要人接待のための御仮屋(仮御殿)として利用されてきました。江戸時代末期まで敷地内には侍の部屋や台所、馬屋など多くの付属施設があり、藩主や来賓をもてなす一大拠点となっていました。五代藩主・伊達吉村によって「観瀾亭」と命名され、それ以前は「月見御殿」とも呼ばれていました。
建物は木造平屋、寄棟こけら葺きで、簡素ながらも格調高い亭風の構造を持っています。内部の「御座の間」には金箔や極彩色で描かれた豪華な障壁画が設えられ、これは狩野派の絵師による江戸時代初期の金碧障壁画として優れた価値を有しています。こうした建築美と歴史的背景から、建物本体は1953年に宮城県の有形文化財に指定され、さらに内部の障壁画は1980年に国の重要文化財に指定されています。
現在も観瀾亭は松島町の管理のもと一般公開されており、抹茶や菓子を味わいながら往時の風情を感じられる憩いの場として親しまれています。この歴史的建造物の保存・維持に献身されてきた関係者および運営者の皆様に深い敬意が表されます。
(2025年8月執筆)
PHOTO:写真AC