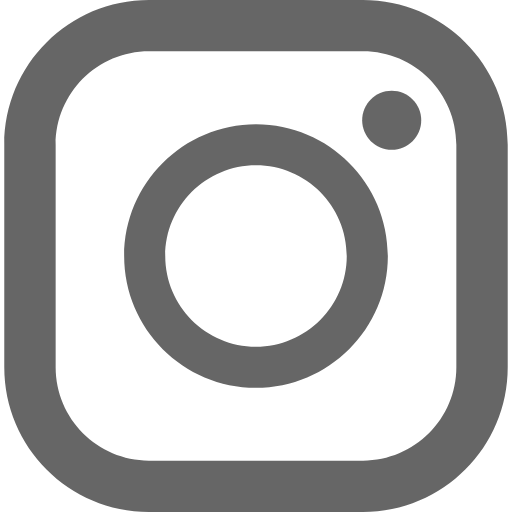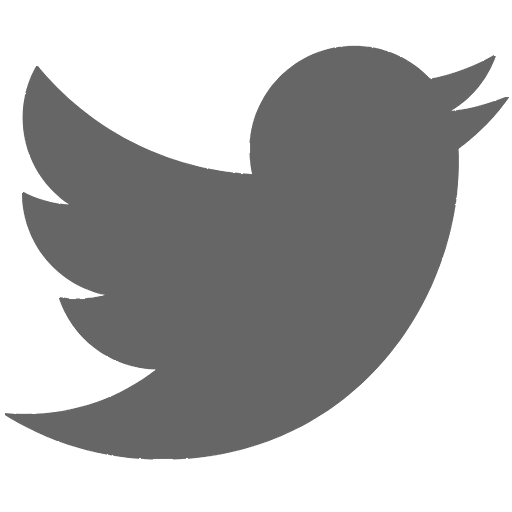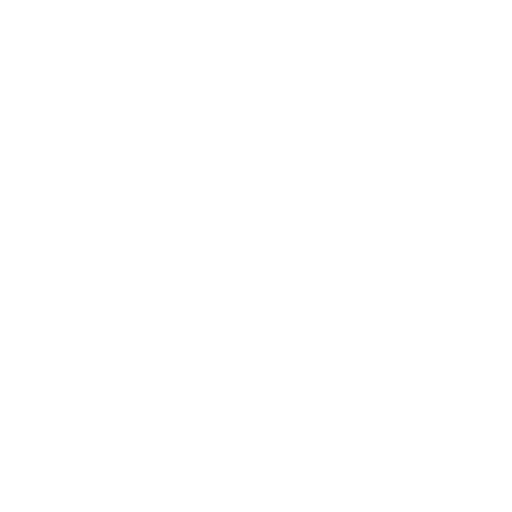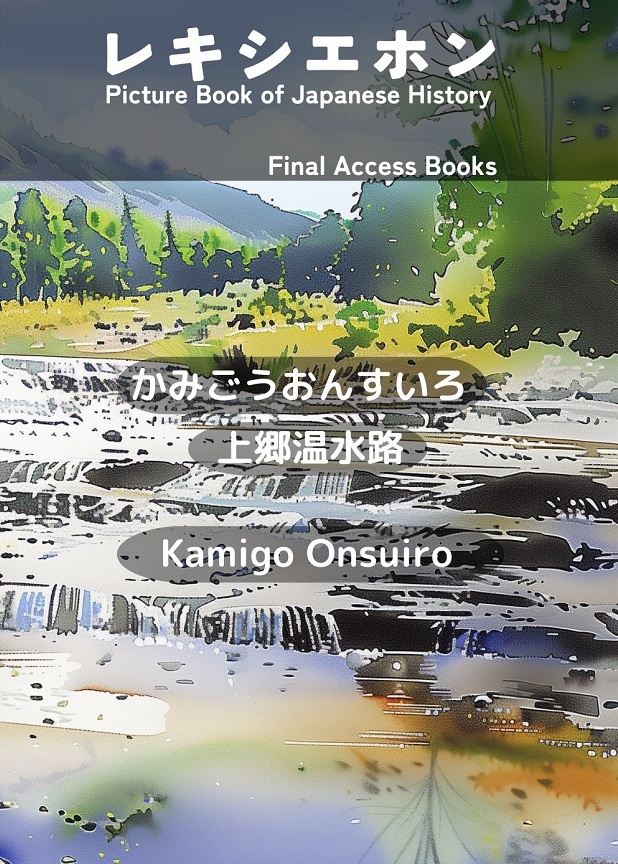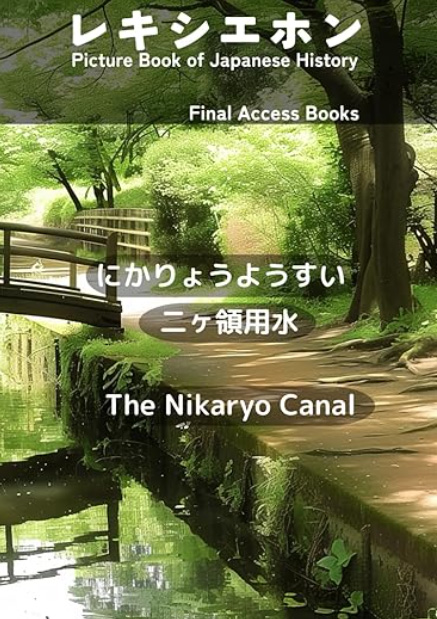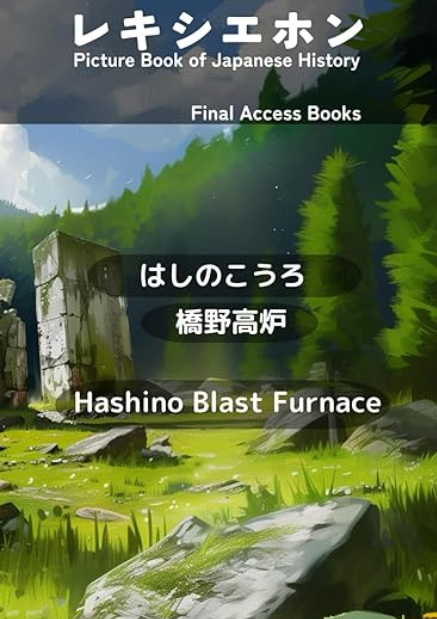釜石鉱山
- 文化・教育施設
日本の近代製鉄発祥の地として知られる岩手県の釜石鉱山は、国の産業史を語る上で欠かせない存在です。その歴史は江戸時代末期の1857年、盛岡藩士・大島高任が日本で初めて洋式高炉による鉄の連続生産に成功したことに始まります。これは、外国の脅威に対抗するため、鉄製大砲の国産化を目指した国家的な課題への挑戦でした。
明治時代に入り、政府による官営化は一度失敗に終わりますが、1887年に民間の実業家・田中長兵衛が事業を引き継ぎ、幾多の困難の末に製鉄業を軌道に乗せました。1894年には日本初のコークス高炉の稼働にも成功し、その技術と人材は後の官営八幡製鉄所の設立に大きく貢献し、日本の重工業の礎を築きました。
その後も日本の産業を支え続けましたが、時代の変化と共に1993年に鉄鉱石の採掘を終了し、鉱山としての長い歴史に幕を下ろしました。しかし、その価値が失われることはありませんでした。大島高任が最初に成功を収めた高炉跡を含む「橋野鉄鉱山」は、2015年に「明治日本の産業革命遺産」の構成資産としてユネスコ世界遺産に登録されました。また、閉山後の広大な坑道は、ミネラルウォーター「仙人秘水」の製造や最先端の学術研究の場として活用され、新たな価値を生み出し続けています。
釜石鉱山の歴史を未来へと繋ぐ運営主の皆様には、多大な敬意が表されます。歴史ファンの皆様、日本の近代化を支えた鉄の都の息吹を、ぜひ現地で体感してください。
(2025年9月執筆)

旋盤工場跡です。
PHOTO:写真AC
VIDEO : Final Access ファイナルアクセス