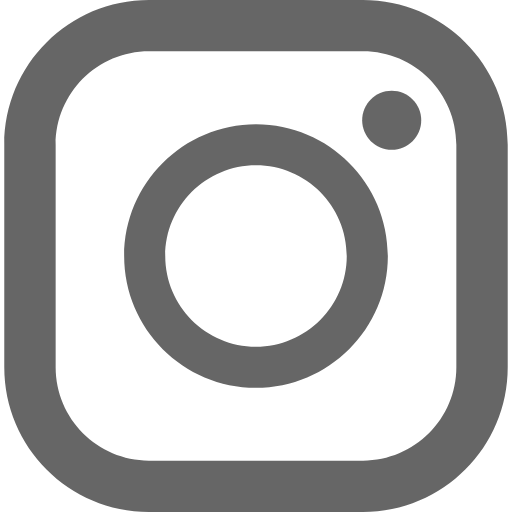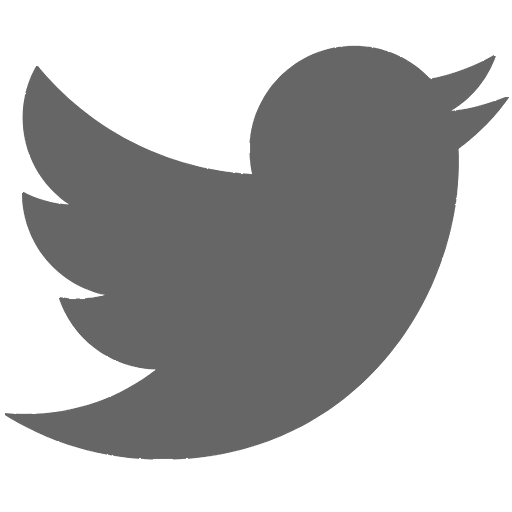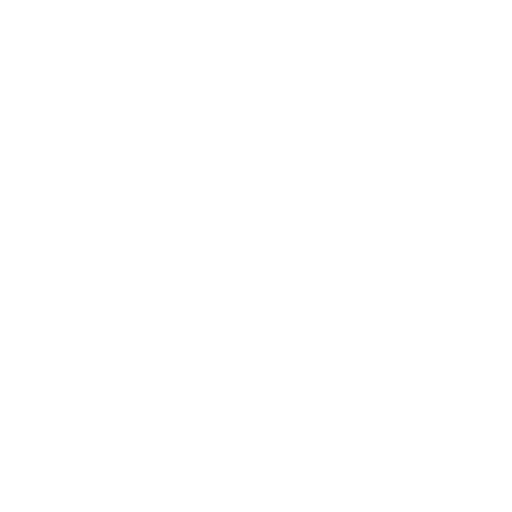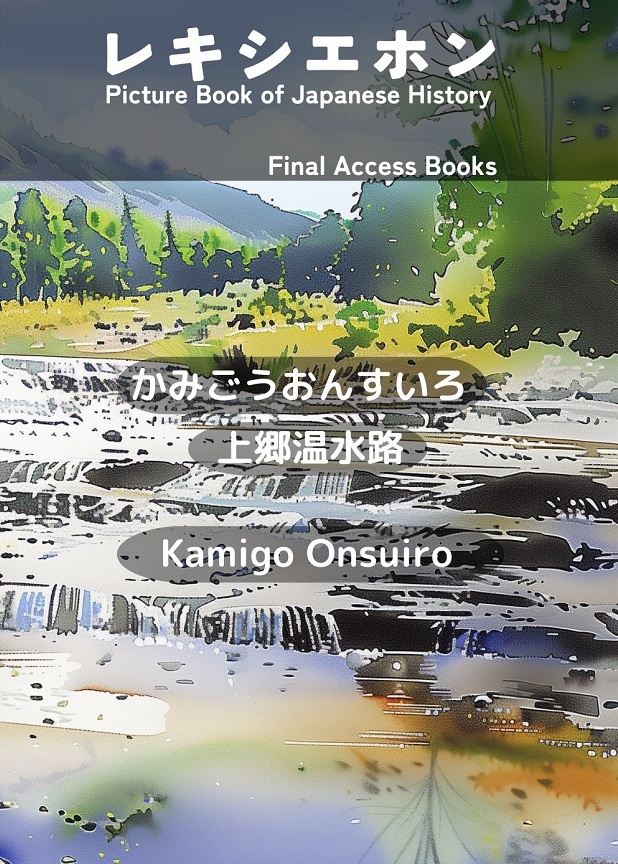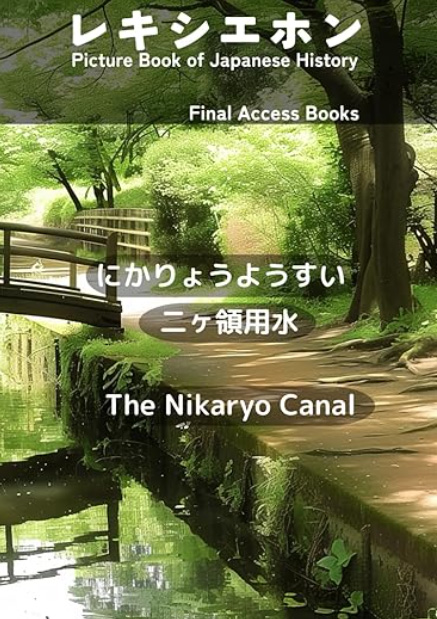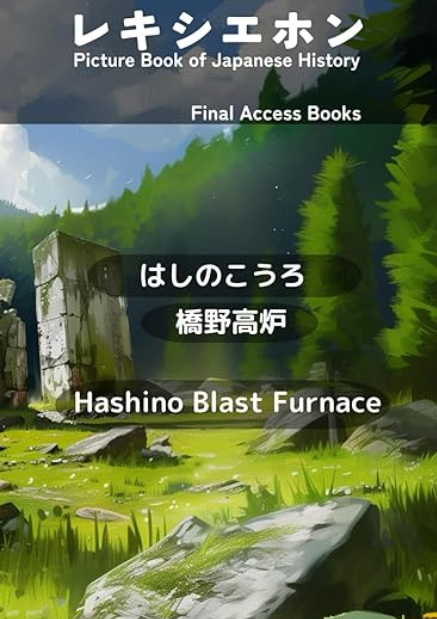美保関おかげの井戸
- 文化・教育施設
島根県松江市美保関町は、江戸時代に日本海航路の要衝として、北前船の寄港地として大いに栄えた港町です。その町の中心、えびす様の総本社である美保神社の鳥居前に静かに佇む「美保関おかげの井戸」は、この町の繁栄と人々の暮らしを支えた歴史の証人です。
この井戸が誕生したのは、幕末の1861年です。その年の夏、地域一帯が深刻な干ばつに見舞われ、町中の井戸がことごとく枯れ果ててしまいました。伝承では、美保大明神のお告げに従いこの場所を掘ったところ、清らかな水がこんこんと湧き出し、町全体が救われたと伝えられています。この奇跡的な出来事から、感謝を込めて「おかげの井戸」と名付けられました。井戸は「廻船御用水」という別名でも呼ばれ、地域住民の貴重な水源であったことはもちろん、寄港する北前船への水供給という極めて重要な役割を担っていました。良質な真水を安定して供給できるこの井戸は、まさに港町・美保関の経済を支える生命線の一つだったのです。
時代は流れ、2007年にはその歴史的価値が公に認められます。井戸単体としてだけでなく、美保関の歴史的な町並みと景観を形成する不可欠な要素として評価され、「国土の歴史的景観に寄与しているもの」として国の登録有形文化財に登録されました。
現在も往時の面影を色濃く残すこの井戸からは、信仰を心の支えとし、海運交易と共に生きた人々の営みをうかがい知ることができます。この貴重な文化遺産を今に伝え、維持管理されている地域の方々には、深く敬意が表されます。歴史ファンの方は、かつての港町の賑わいに思いを馳せながら、ぜひこの地を訪れてみてはいかがでしょうか。
(2025年11月執筆)
PHOTO:写真AC