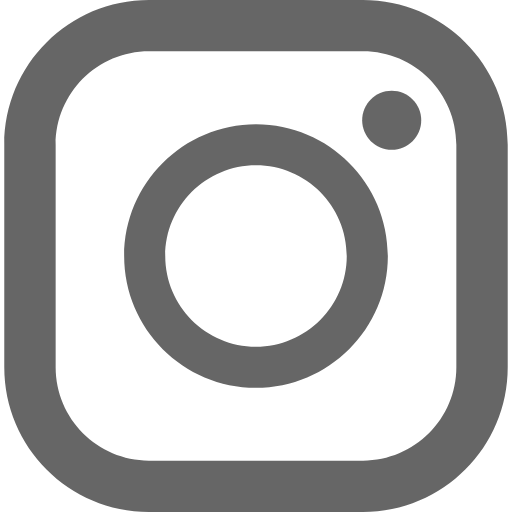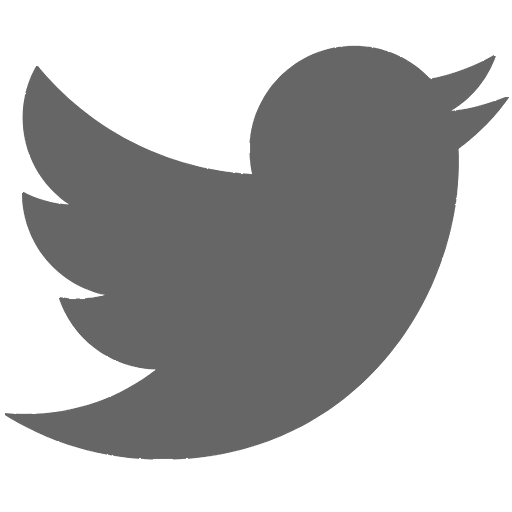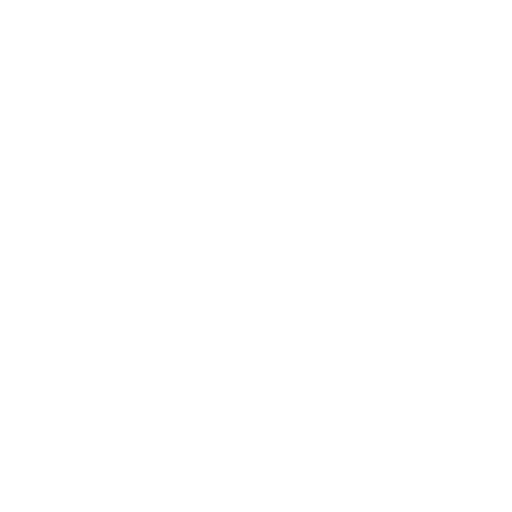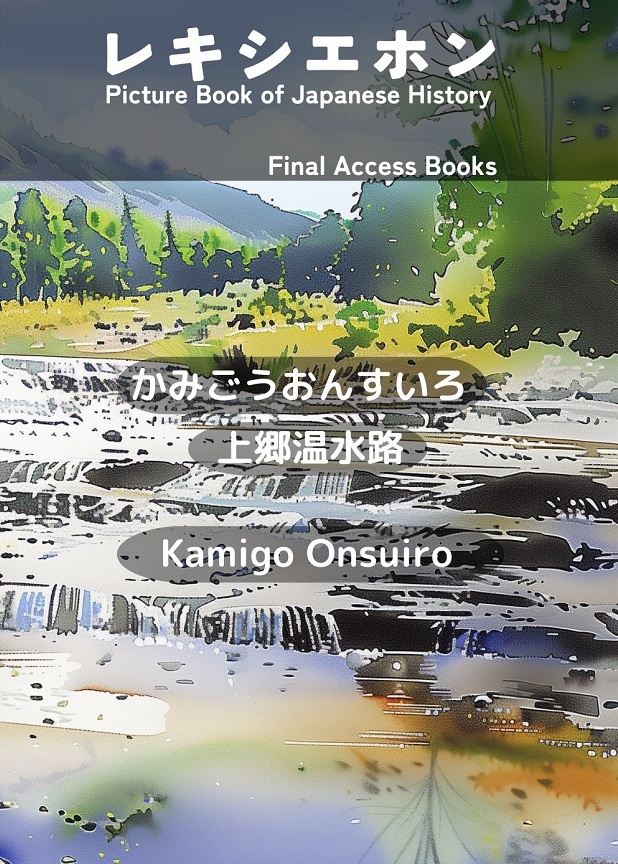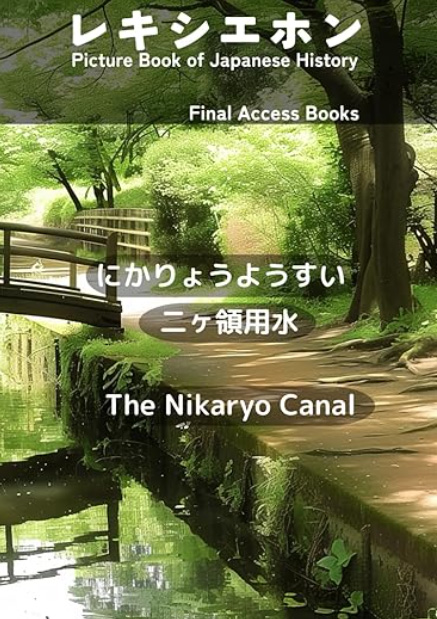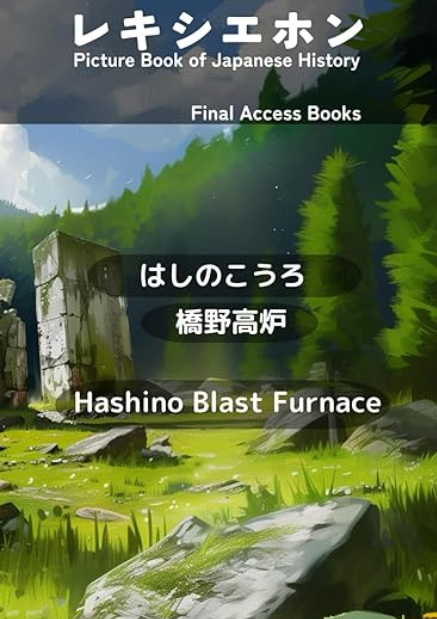住吉大社 御文庫
- 文化・教育施設
住吉大社の神苑に静かに佇む御文庫は、1723年に大坂、京都、江戸の書籍商たちによって建立された、大阪最古の図書館とも称される歴史的建造物です。その設立には、商売繁盛を願う信仰心と、出版業を守るための巧みな実利主義が込められていました。
当時、出版の中心地であった大坂の書籍商たちは、文学の神として信仰を集める住吉大社に、出版した本の初版を奉納しました。これは神への祈願であると同時に、増刷で版木が摩耗した際の原版となり、また火災多発の時代にあって版木を失った際のバックアップとしても機能する、優れた共同保険制度でした。1837年の大塩平八郎の乱では、大阪天満宮にあったもう一つの御文庫が焼失しましたが、住吉は難を逃れ、唯一無二の存在としてその歴史的価値を一層高めることになります。
明治時代に入ると、書籍商たちの組合である「講」は再編・統合され、「大阪書林御文庫講」として現代に至るまで約300年間、活動を絶やすことなく続けています。建物は昭和期に現在地へ移築され、近年修復も行われました。その歴史的価値は公にも高く評価され、2018年には国の登録有形文化財に、その後、大阪府指定有形文化財にも指定されています。
御文庫は、江戸時代から続く大阪の出版文化を今に伝える「生き証人」です。この貴重な文化遺産を三世紀にわたり守り継いできた大阪書林御文庫講の関係者の方々には、深く敬意が表されます。歴史ファンであれば、ぜひ一度その歴史の重みに触れてみてはいかがでしょうか。
(2025年10月執筆)
PHOTO:写真AC