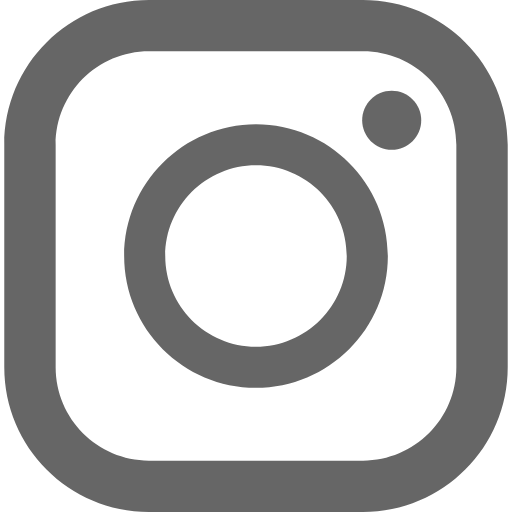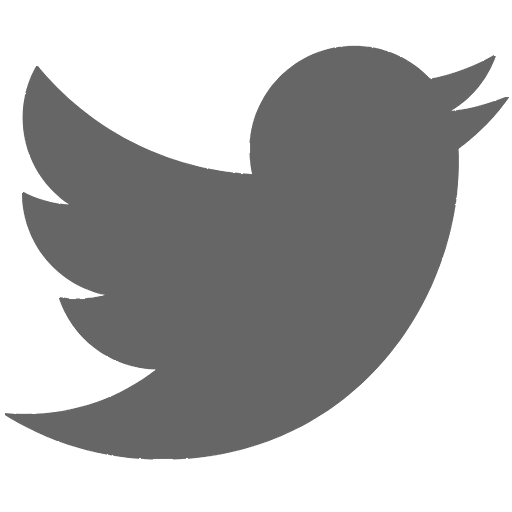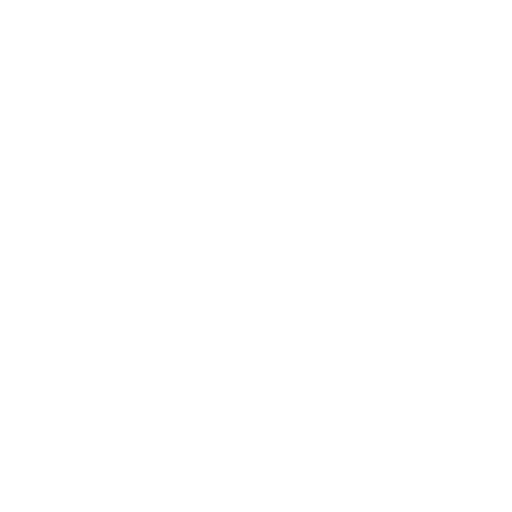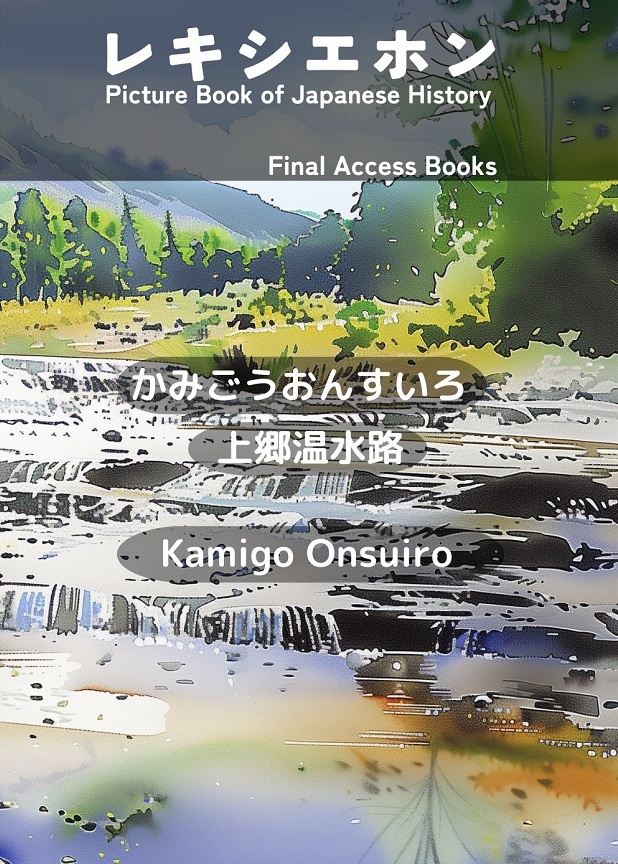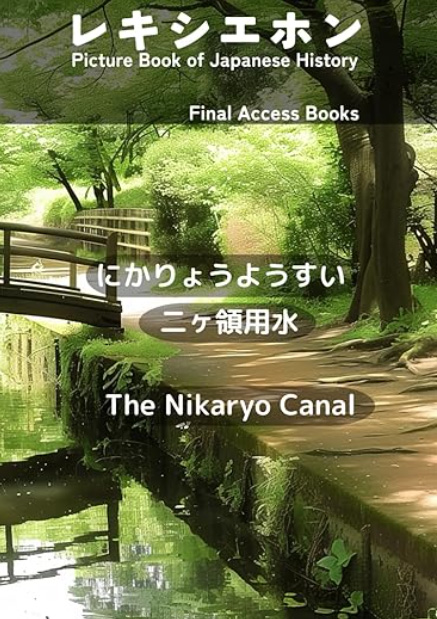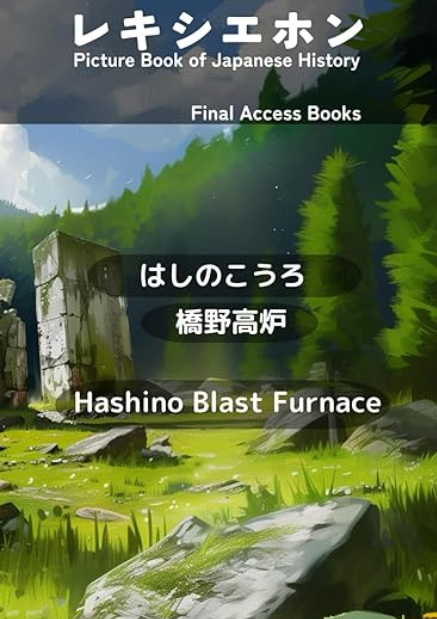東京商船大学旧天体観測所
- 文化・教育施設
東京海洋大学越中島キャンパスの一角に佇む旧天体観測所(第一観測台・第二観測台)は、近代日本の海事教育の黎明期を今に伝える貴重な歴史遺産です。商船教育において、船舶の位置を正確に知るための天測は必須の技術であり、そのための天文学教育の中心地として機能しました。この観測所が建設された背景には、東京商船学校(東京海洋大学の前身の一つ)が1901年に越中島へ移転し、施設を拡充する流れがありました。観測台は、移転から約2年後の1903年3月に竣工しました。設計は、逓信技師であった三橋四郎が手掛けたものと推定されています。
特に第一観測台は煉瓦造の2階建てで、ドーム屋根を持つその構造は、現存する日本最古級の天文台ドーム形状の観測室であると推定されています。ここには、当時「東洋一」と称されたイギリス製の赤道儀望遠鏡が設置され、海運の未来を担う学生たちが天体運行の知識を深めました。また、隣接する八角錐屋根の第二観測台には子午儀が備えられ、正確な経度や時刻の決定に用いられました。
観測所は、1923年の関東大震災や1945年の東京大空襲という激動の時代においても焼失を免れ、震災後には御真影の仮奉安所としても利用された歴史を持ちます。戦後に望遠鏡本体は失われたものの、建物は残り続けました。その歴史的・建築的な価値は高く評価されており、1997年には両観測台が国の登録有形文化財に登録されました。さらに、2021年には日本天文学会により日本天文遺産に認定され、その学術史上の重要性が改めて公的に認められています。
この貴重な歴史的建造物を維持管理されている東京海洋大学様には、深く敬意が表されます。日本の海運と科学の歴史を体現するこの場所に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
(2025年11月執筆)
PHOTO:PIXTA