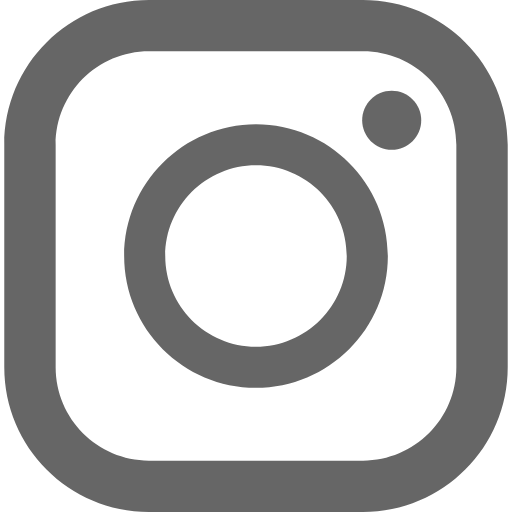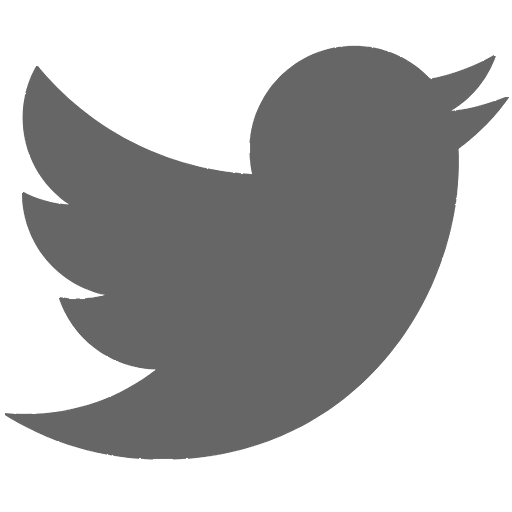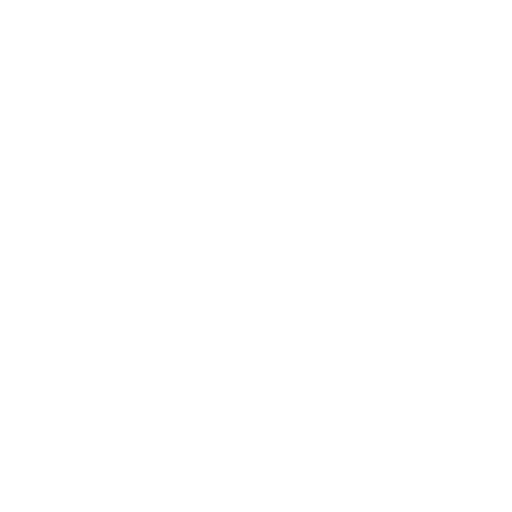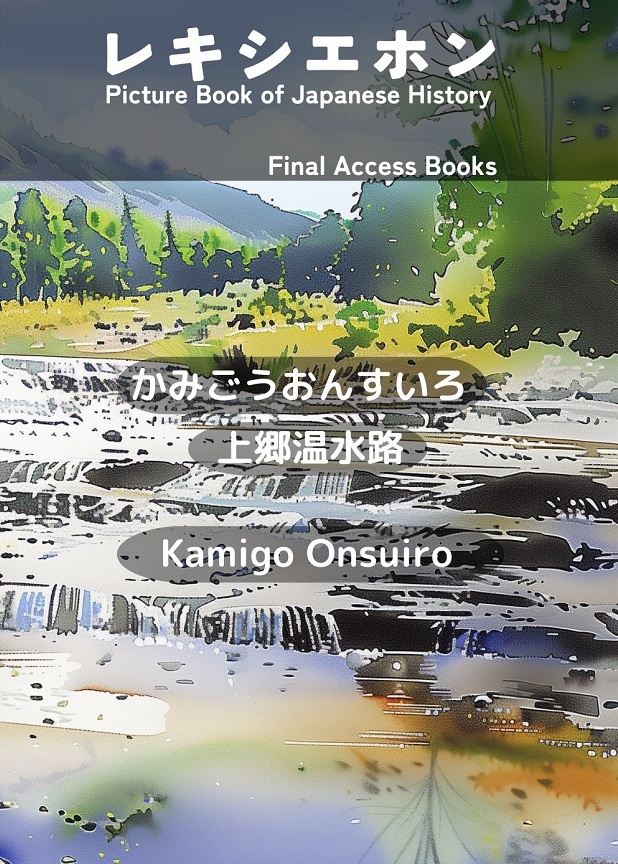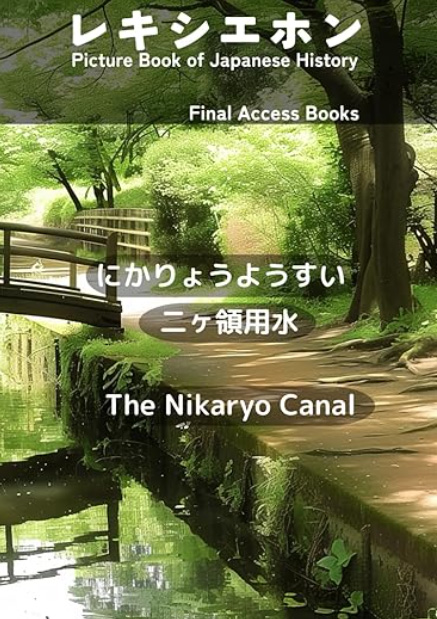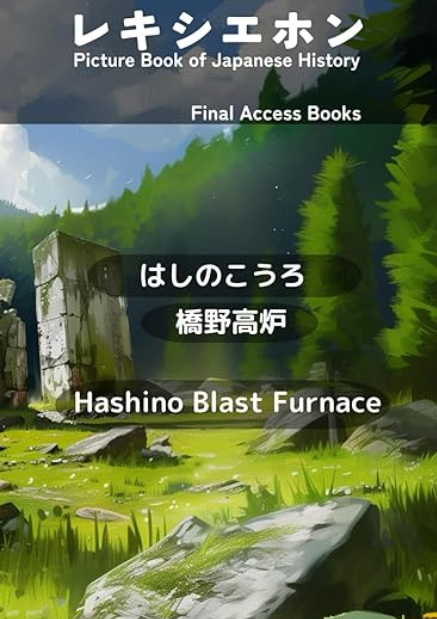晩香廬
- 文化・教育施設
晩香廬は、「日本資本主義の父」と称される渋沢栄一が晩年を過ごした、東京都北区の旧渋沢家飛鳥山邸(曖依村荘)内に現存する貴重な木造洋風小建築です。
その歴史は、栄一が七十七歳の喜寿を迎えたことに始まります。1916年、渋沢翁が第一国立銀行設立の際に恩顧を受けた合資会社清水組(現・清水建設)の清水満之助氏が、長年の恩義に報いるため、バンガロー式小亭の建設を目録とともに献呈しました 。この建物は、清水組技師長であった田辺淳吉氏が設計監督を担当し、1918年に竣工しています 。
晩香廬という名称は、栄一自身が自作の漢詩「菊花晩節香」 から名付けたもので、「晩節の香り」として、自身の人生終盤への決意が込められていました。この建物は、洋風の外観に長い庇や屋根の形といった日本家屋の要素を取り入れた雅趣に富んだ和洋折衷のデザインが特徴です。栄一は晩年、国内外の賓客をもてなすための小亭(談話室) として晩香廬を愛用しました。暖炉や家具などの調度品まで設計者の細やかな配慮が見られ、イギリスのウィリアム・モリスが提唱したアーツ・アンド・クラフツ運動の精神を具現化した大正期を代表する建築作品として、美術工芸的な価値も非常に高いと評価されています 。
1945年の東京大空襲では、隣接する青淵文庫とともに主要な建物が焼失するなかで戦禍を免れ、その姿を現代に伝えています 。当地において晩香廬は、飛鳥山邸の歴史を証言する貴重な遺構であり、偉人渋沢栄一の晩年の交流の場として重要な位置を占めています。晩香廬の歴史的価値は公に認められており、2005年には「旧渋沢家飛鳥山邸 晩香廬」として、青淵文庫とともに 国の重要文化財に指定され 、その建築美と歴史的意義は不動のものとなっています。
現在までこの歴史ある建物を大切に守り、広く公開している運営管理主体の皆様には、深く敬意が表されます。大正モダンの洗練された空間と、渋沢栄一翁の功績を感じるために、歴史ファンの皆様にはぜひ一度当地を訪問されることをお勧めいたします。
(2025年11月執筆)
PHOTO:PIXTA