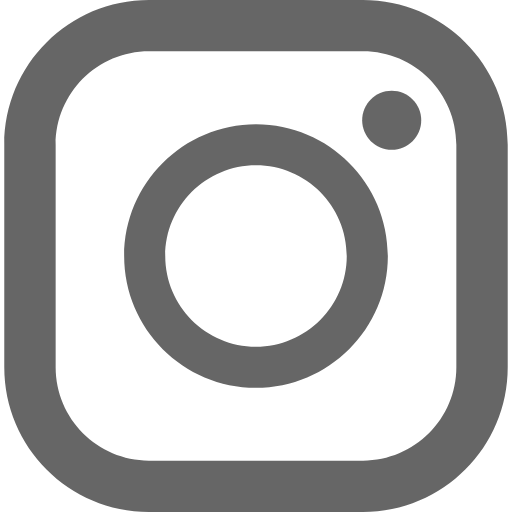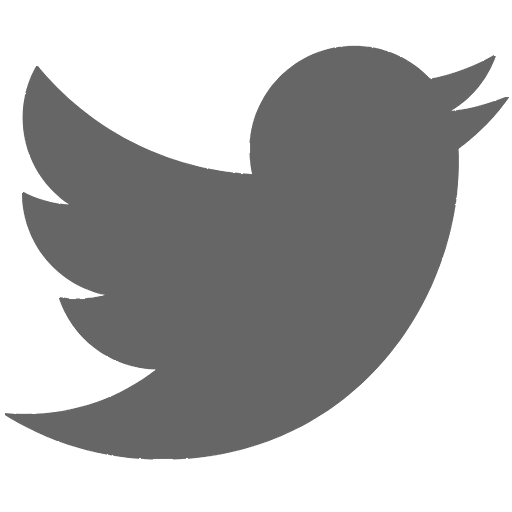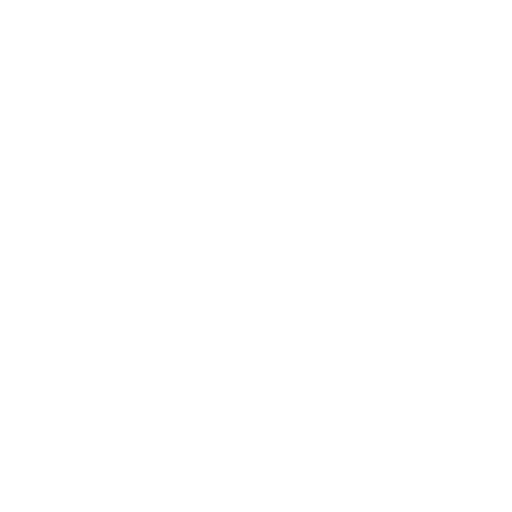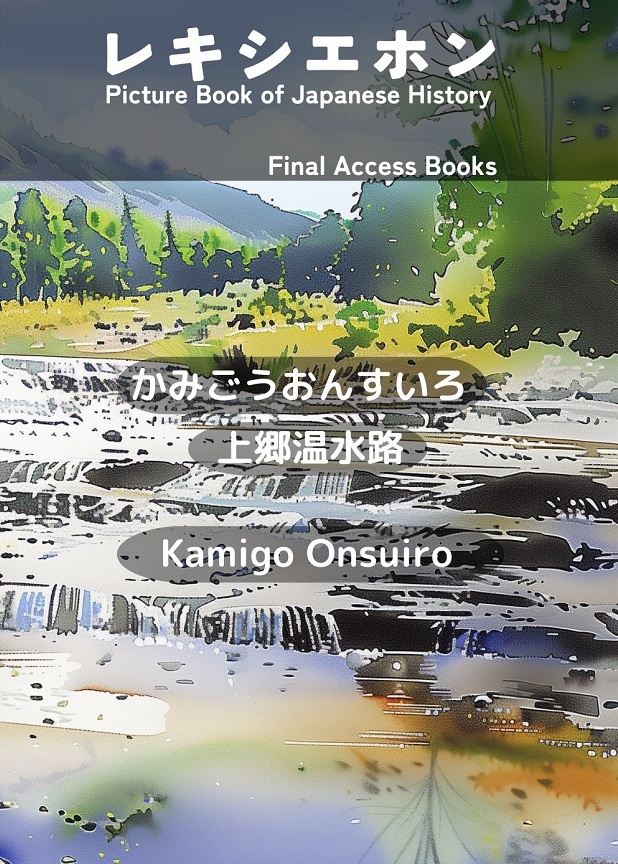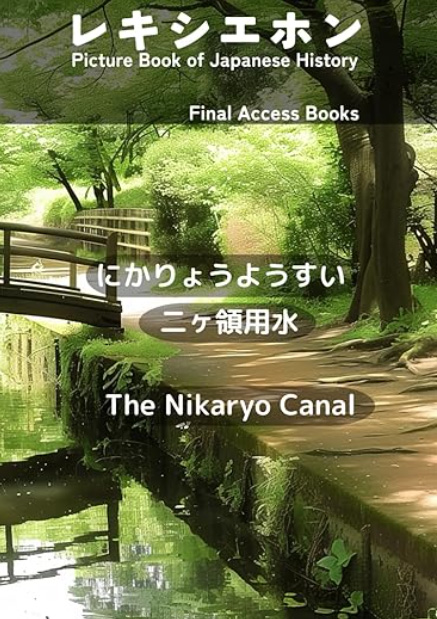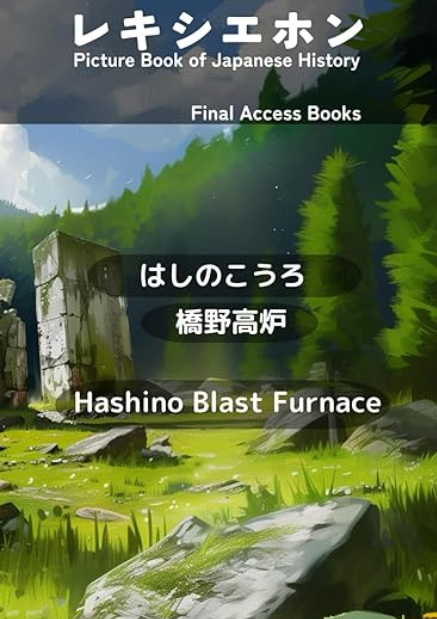函館山砲台跡
- 文化・教育施設
函館山の砲台跡は、近代日本の対外防衛強化と地域防衛意識の高まりを象徴する遺構です。その起源は、19世紀後半、西洋列強の来航や箱館戦争を経て、津軽海峡の戦略的重要性が認識されたことに始まります。帝政ロシアをはじめとする北方軍事圧力に備えるため、1890年代から1902年頃にかけて山頂付近に大規模な要塞群が築かれました。要塞群には榴弾砲を備えた砲台が配置され、海峡防備の拠点として機能しました。
これら砲台は地域住民や技術者による労力で建設され、都市函館と深いつながりを持ちました。大正から昭和初期にかけては軍事施設としてその存在感を保ち、日露戦争などの緊張時には地域の安全確保に大きな役割を果たしました。一方で、砲台建設や維持には地元経済への影響も及び、多くの人々が工事や関連事業に従事しました。第二次世界大戦終結後、軍事的価値は失われ、砲台は順次閉鎖・撤去されていきました。遺構は草木に埋もれながらも保存され、市民や観光客に戦争遺産として公開されるようになりました。現在は平和学習や歴史体験の場となり、函館の風景と相まって地域の文化資源となっています。
函館山砲台跡の長い歴史は、地域の防衛意識と暮らし、平和の大切さを静かに伝えています。この歴史的遺構の管理・保存に尽力されている関係者の皆様に、心より敬意を表します。
(2024年10月執筆)

歴史を今に伝える貴重な史跡です。
PHOTO:写真AC