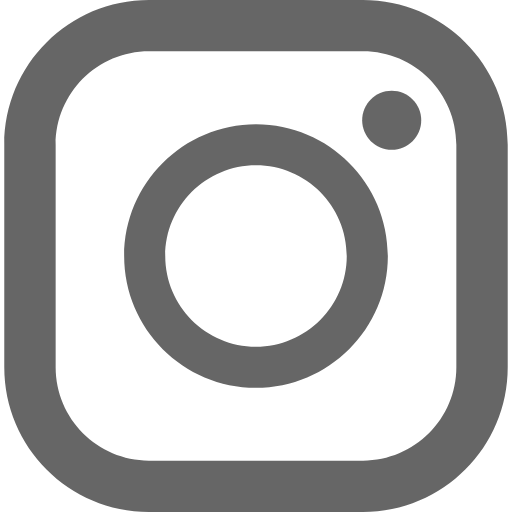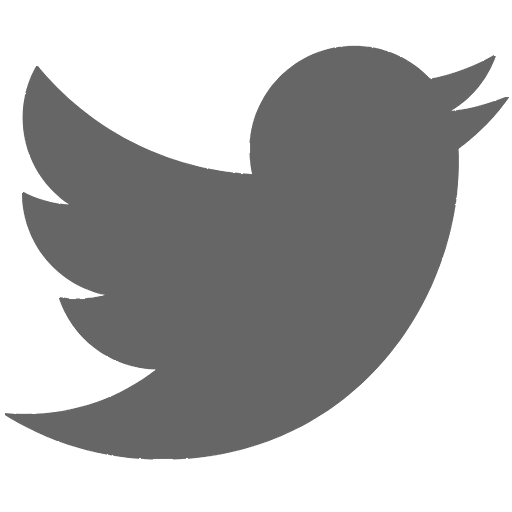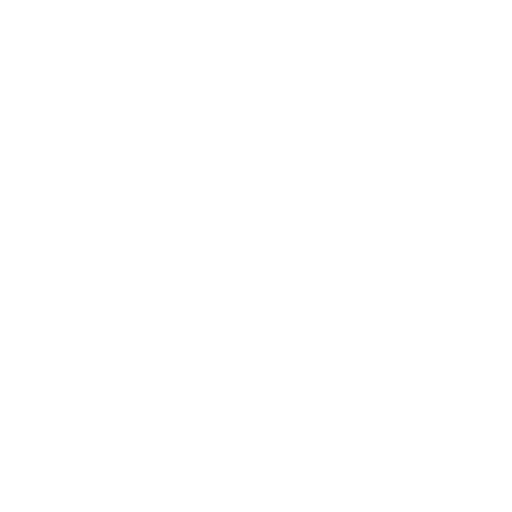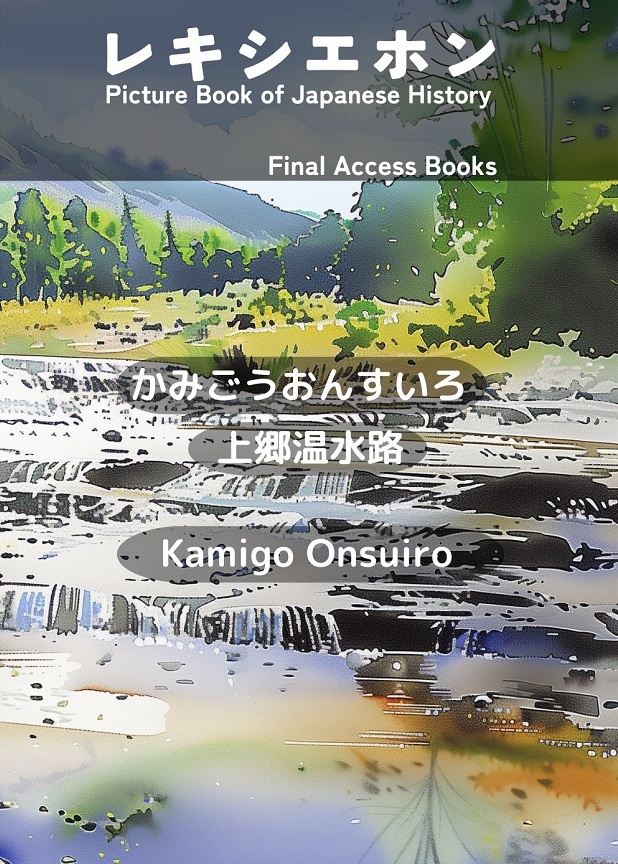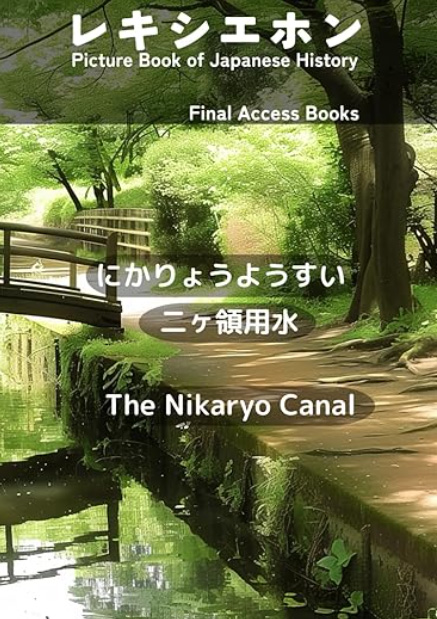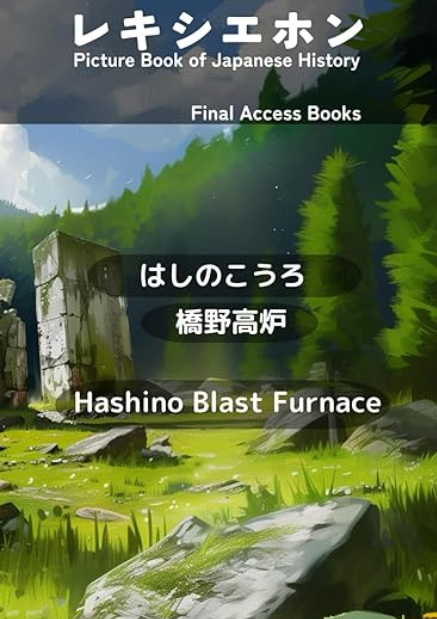旧中島浄水場配水塔
- 文化・教育施設
長岡市の水道公園に静かに佇む「旧中島浄水場配水塔」は、市民から「水道タンク」の名で親しまれ、街の歴史を見守り続けてきた大切なランドマークです。その誕生は、20世紀初頭の長岡市が直面した深刻な課題に遡ります。1906年の市制施行後、産業の発展とともに市は急成長を遂げましたが、水道インフラの未整備から水質は劣悪で、伝染病の流行が市民の健康を脅かすなど、安全な水の確保は待ったなしの状況でした。この公衆衛生の危機を乗り越え、近代都市として発展するため、市は最先端の水道施設建設という大きな決断を下します。
設計は1923年に始まり、1926年に建設工事が着工されました。指導にあたったのは、関東大震災の教訓から耐震建築の礎を築いた内田祥三博士です。鉄筋コンクリート造の堅牢な構造と、ドイツの先進技術である「インゼ式」を採用したこの配水塔は、まさに当時の技術の粋を集めたものでした。そして1927年、信濃川の水を浄化して市民へ届ける近代水道の心臓部として、ついに運転を開始し、長岡の暮らしと健康を支える基盤となったのです。その歴史は平穏ではなく、1945年の長岡空襲では、外壁に280発もの弾痕を刻まれながらも、その頑強な躯体は致命的な損傷を免れました。焦土と化した街で、復興に不可欠な水を供給し続けたその姿は、市民にとって不屈の精神と希望の象徴となりました。
戦後も市民生活を支え続けましたが、1993年に66年間の長きにわたる役目を終えました。一時は解体も検討されましたが、その歴史的価値を未来へ伝えようという声が高まり、1996年に保存が決定。翌1997年度に大規模な改修工事が行われ、創建当時の姿を留めながら美しく生まれ変わりました。そして1998年、国の登録有形文化財となり、その技術的・歴史的価値が改めて高く評価されました。
今日、水道公園のシンボルとして愛される配水塔は、映画のロケ地となるなど、新たな文化的役割も担っています。その姿は、長岡の近代化、戦争からの復興、そして現代へと続く人々の歩みを静かに語りかけ、市民の記憶と現在を結びつけるかけがえのない宝物として、今も街を見守っています。
(2025年7月執筆)
PHOTO:PIXTA
映画「この空の花-長岡花火物語」は、2011年夏、熊本の地方紙記者・遠藤玲子が新潟県長岡市を訪れ、中越地震から復興し東日本大震災の被災者を受け入れた町を取材する物語です。元恋人からの手紙や女子生徒の反戦劇を通じて、長岡空襲や花火大会の歴史、市民の復興への祈り・平和への願いと向き合い、過去・現在・未来を繋ぐ壮大な時間の旅が描かれます。
旧中島浄水場配水塔(水道タンク)がある「水道公園」一帯でロケが行われました。映画でも戦争や復興の象徴的な場所として登場します。