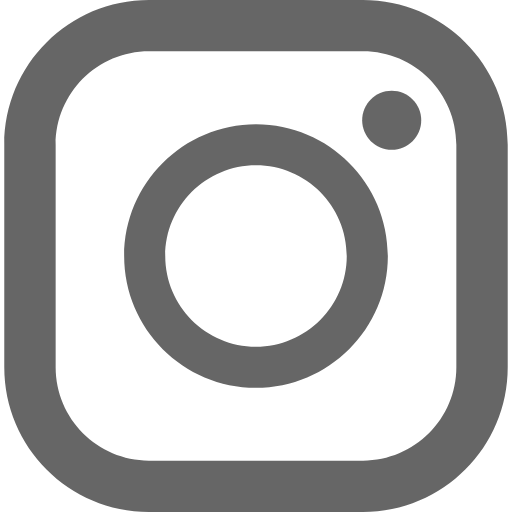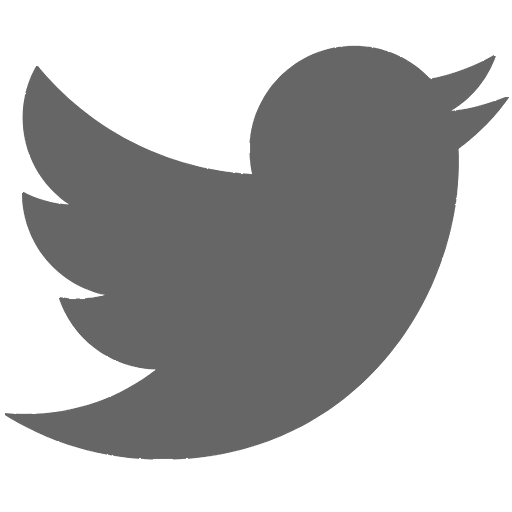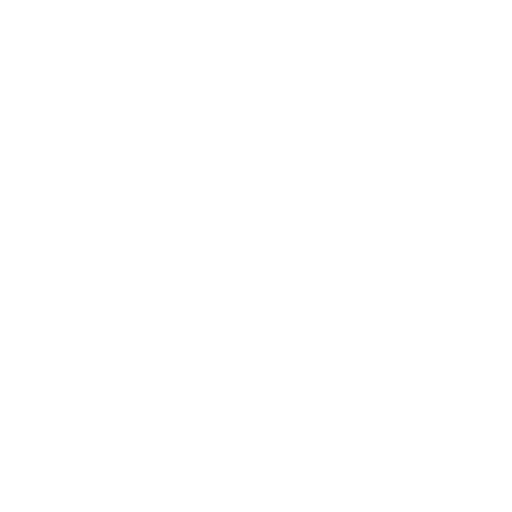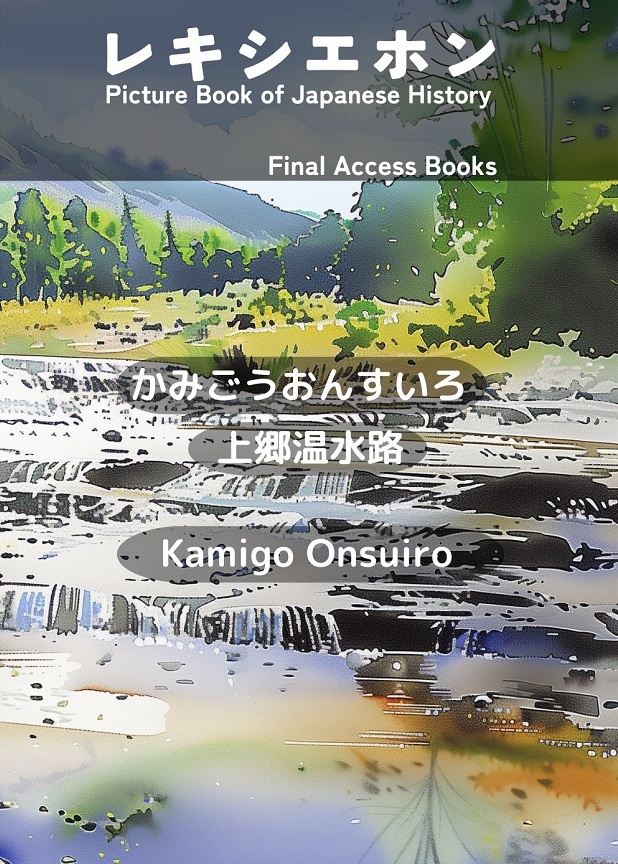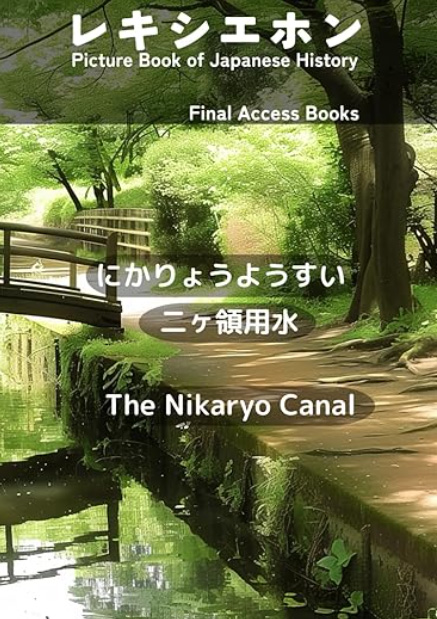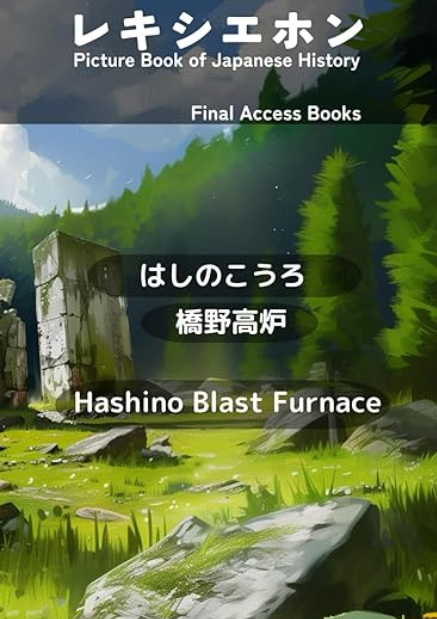久地円筒分水
- 文化・教育施設
川崎市高津区に静かに佇む久地円筒分水は、水を巡る長い闘争の歴史に終止符を打った、技術と平和の象徴です。
その源流は、江戸時代初期にまで遡ります。1597年から徳川家康の命を受けた代官・小泉次大夫が約14年の歳月をかけて開削した二ヶ領用水は、多摩川から水を引き、地域の農業を支える大動脈でした 。しかし、用水に頼る水田が増えるにつれて水不足が深刻化し、上流と下流の村々の間で水を奪い合う「水争い」が頻発するようになります 。特に1821年に発生した「溝口村水騒動」は、名主の家が打ち壊されるほど激しいもので、用水史上最大の争いとして記録されています 。当時の分水方法は水路の幅を仕切る単純なもので、正確な分水が技術的に難しく、不公平感と不信の火種となっていました 。
この数世紀にわたる深刻な対立を解決するため、1941年に画期的な施設、久地円筒分水が建設されました 。設計者は、当時の多摩川右岸農業水利改良事務所長であった平賀栄治です 。この施設は、平瀬川の下をサイフォンの原理でくぐらせた用水を円筒の中央から噴き上がらせ、外側の円筒の縁から溢れさせます。その縁を各水路が潤す灌漑面積の比率に応じて仕切ることで、誰の目にも公平な分水を完璧に実現しました 。この視覚的な公平性こそが、長年の争いを根本から解決する鍵となったのです。
戦後の都市化により農業用水としての役割はほとんど終えましたが、その歴史的・技術的価値は高く評価され、1998年には川崎市で初となる国の登録有形文化財に登録されました 。今日では、春には桜が美しく咲き誇り、市民の憩いの場として親しまれています 。長きにわたりこの貴重な歴史遺産を維持管理されてきた関係各位には、深く敬意が表されます。水の歴史と先人たちの知恵が結晶したこの地は、歴史ファンなら一度は訪れるべき場所と言えるでしょう。
(2025年10月執筆)
PHOTO:写真AC