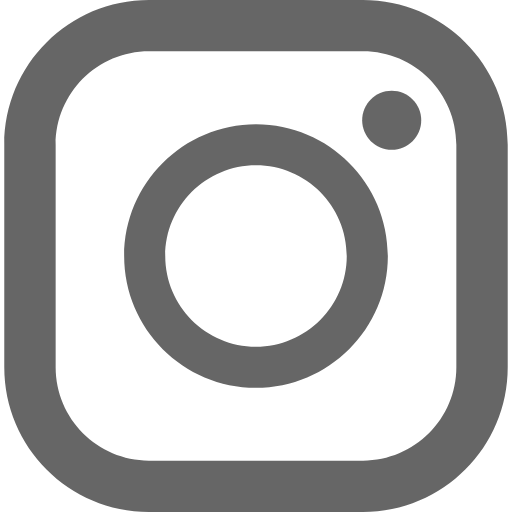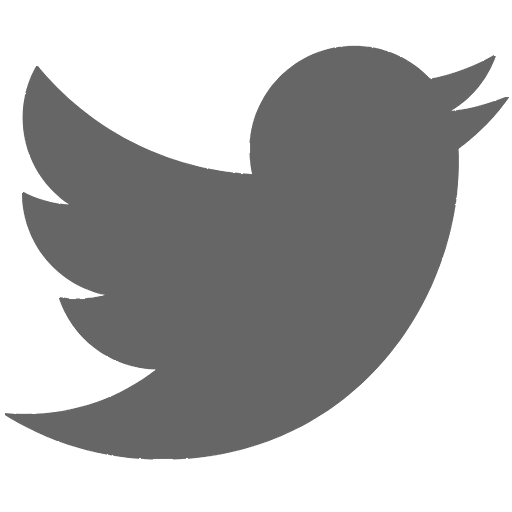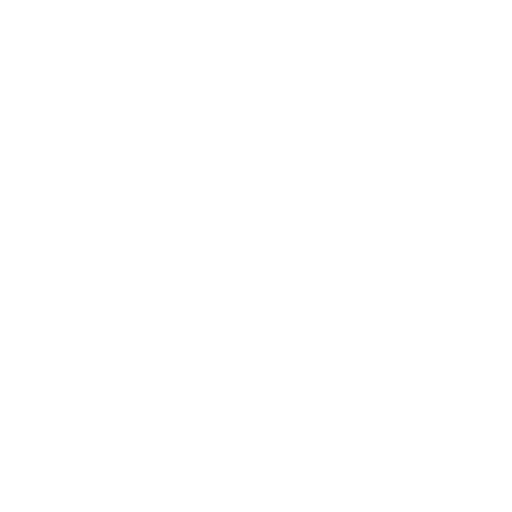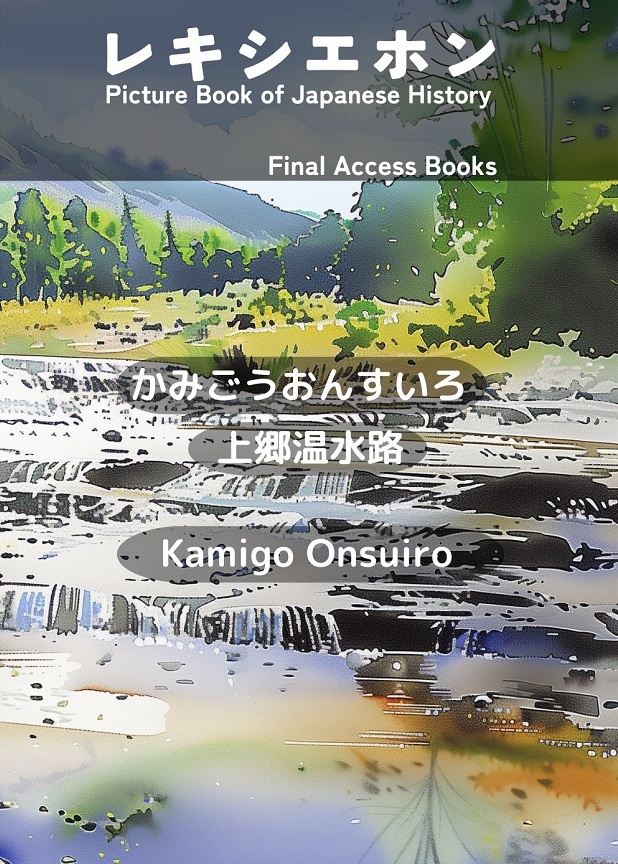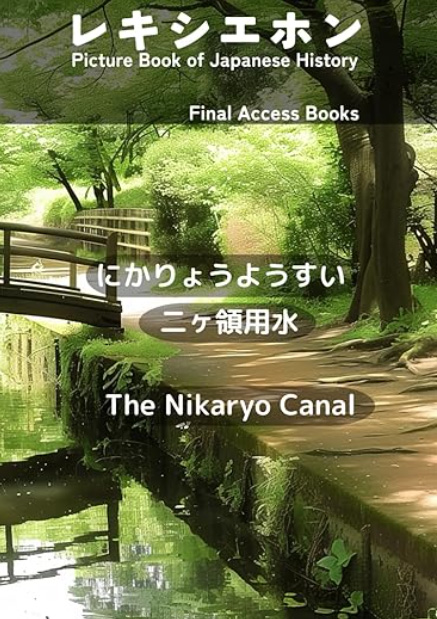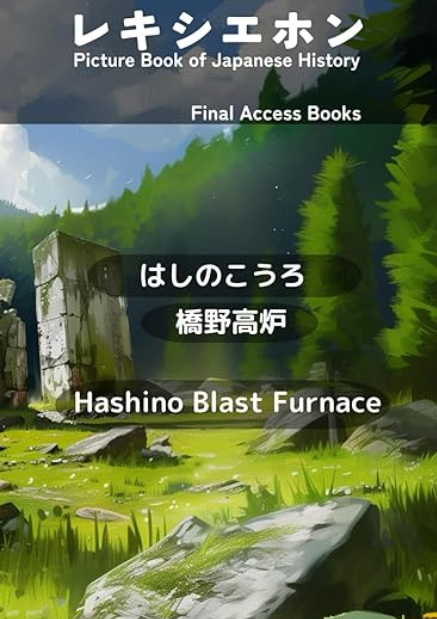本宮砂防ダム
- 建物・施設
富山の守護神、本宮砂防ダムの軌跡富山平野を潤す常願寺川は、かつて「暴れ川」として地域住民に恐れられていました。その歴史を決定づけたのは、1858年に発生した安政飛越地震です。この地震により、源流部の山々が大規模に崩壊。流れ込んだ膨大な土砂は川底を急速に押し上げ、富山平野は未曾有の水害に繰り返し見舞われることとなったのです 。治水は県民の悲願となり、度重なる災害に直面した富山県は、国の直轄事業化を待たずして歴史的な決断を下します。1935年、県単独の緊急事業として本宮砂防ダムの建設に着手したのです 。
当時最新鋭の大型機械を投入し、昼夜兼行の突貫工事の末、わずか2年後の1937年にこの巨大なコンクリート構造物を完成させました 。完成したダムは、日本最大級とされる約500万立方メートルの貯砂量を誇り、幾度となく上流からの土砂を捕捉し、富山平野を水害から守り抜きました 。この功績と、昭和初期の土木技術を今に伝える歴史的価値が評価され、1999年に国の登録有形文化財に登録されます。さらに2017年には、上流の白岩堰堤などと共に「常願寺川砂防施設」として、国の重要文化財に指定されました 。これは個別の施設だけでなく、流域全体を一つのシステムとして捉えた日本の近代砂防技術の達成が、文化遺産として認められたことを示しています 。
現在、ダムは建設から80年以上を経てもなお、防災の要として現役で機能し続ける一方、その周辺は「水辺の楽校」として整備され、市民が自然に親しむ憩いの場ともなっています 。この巨大な構造物を守り、富山平野の安全を支え続けるすべての方々の、絶え間ない努力と使命感に深く敬意を表します。轟音を立てて流れ落ちる水の前に立てば、この地に刻まれた人々の願いと、幾多の記憶が聞こえてくるようです。
(2025年6月執筆)
PHOTO:写真AC