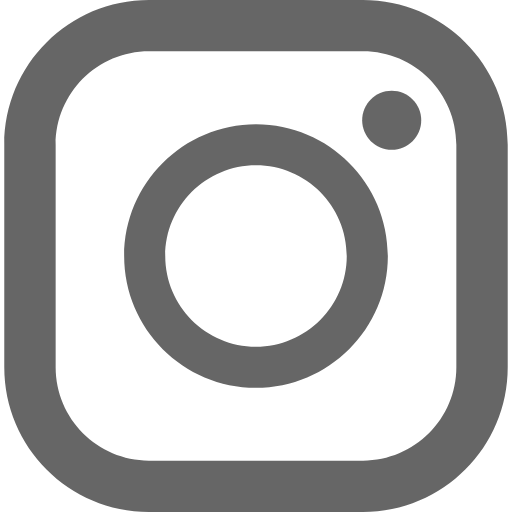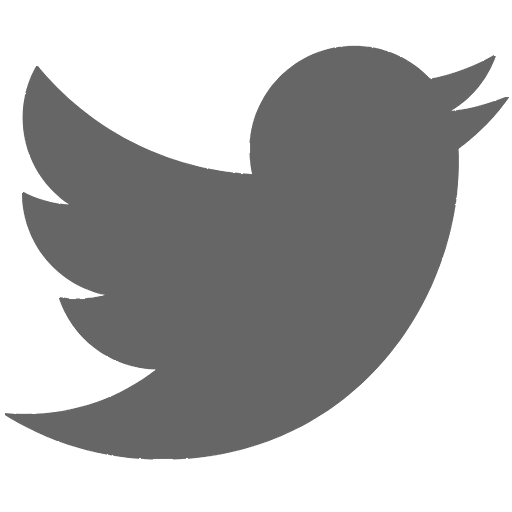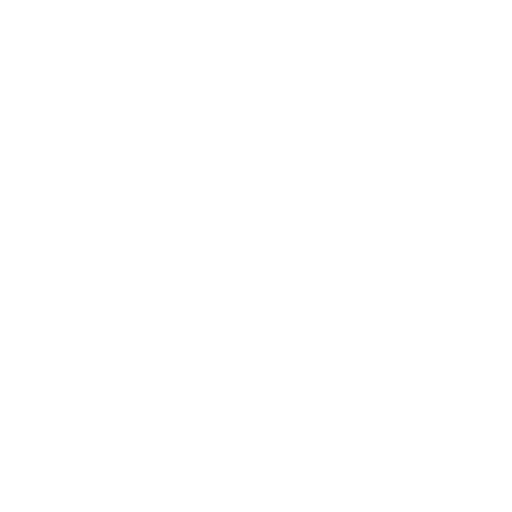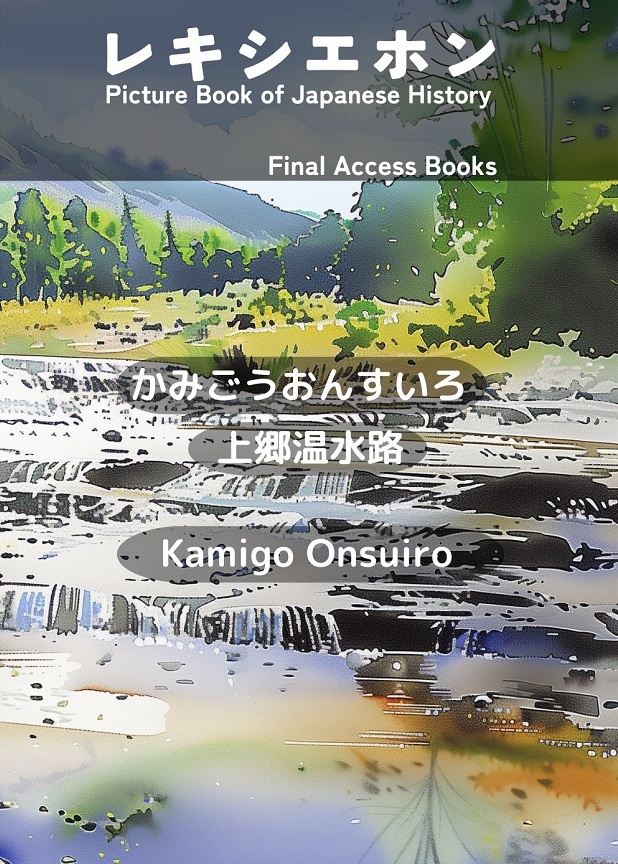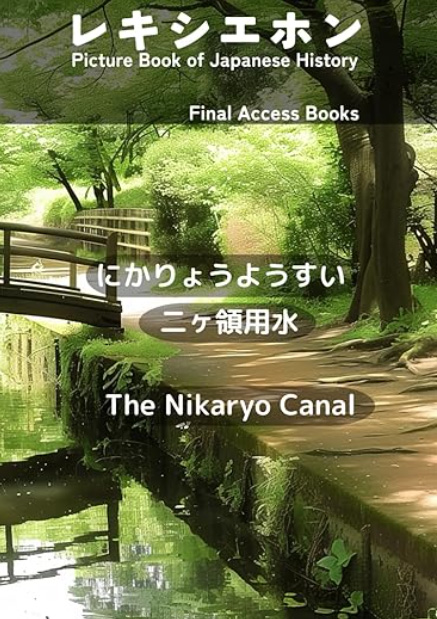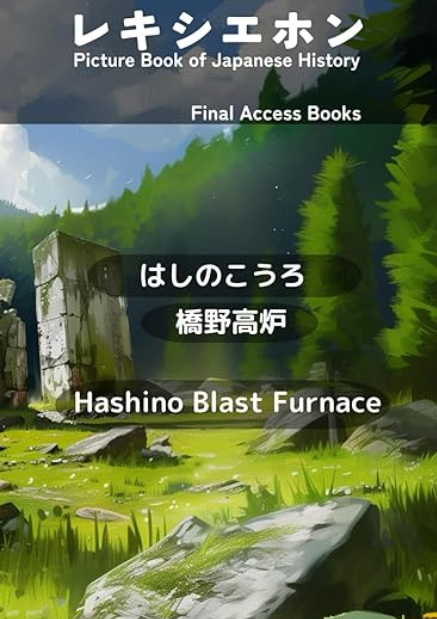【山陽本線】大畠駅舎 解体
- 建物・施設
山口県柳井市、瀬戸内海の穏やかな波がホームのすぐそばまで寄せる場所に、大畠駅はあります。全国でも稀有な「海に最も近い駅」の一つとして知られるこの駅は、今、大きな節目を迎えようとしています。
その歴史は、日本の近代化が力強く進んだ1897年に遡ります。山陽鉄道が広島から徳山へと路線を伸ばした際に開業した大畠駅は、当初から旅客と貨物の両方を扱う地域の交通の要衝でした。1899年には対岸の屋代島(現在の周防大島)への連絡駅となり、島と本土を結ぶ玄関口として、多くの人々の往来で賑わいを見せました。1906年の国有化を経て、1946年には国鉄の鉄道連絡船が就航し、その役割は戦後の復興期において一層重要性を増していきました。
しかし、時代の流れは駅の役割を少しずつ変えていきます。モータリゼーションの進展と共に、1962年に貨物輸送が、1976年には大島連絡船がその役目を終えました。かつての賑わいは、日々の通勤・通学客や地域住民の利用を中心とした、穏やかな日常へと姿を変えました。人口減少の波も押し寄せる中、利用者数は減少傾向にありますが、車を持たない高齢者や学生にとって、駅は今なお暮らしに欠かせない拠点であり続けています。
大畠駅の駅舎は長年地域に親しまれてきましたが、老朽化のため建て替えが決定され、2025年には新駅舎の建設が始まり、現駅舎は夏から秋にかけて解体される予定です。新たな駅舎が地域の新しいランドマークとなる一方で、長年親しまれた駅舎との別れは多くの人々にとって感慨深いものとなるでしょう。大畠駅は時代ごとに役割を変えながらも、地域の生活を支え続けてきました。JR西日本様を始め、運営に携わる全ての方々に敬意を表し、駅舎に刻まれた思い出がこれからも多くの人の心に残ることが望まれます。
(2025年6月執筆)

見慣れた光景とも永遠のお別れです。
PHOTO:PIXTA