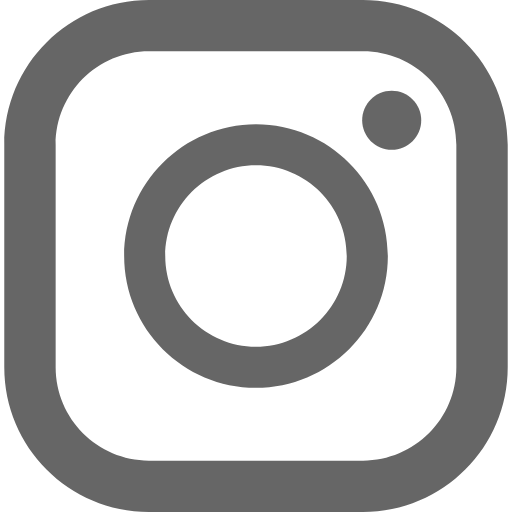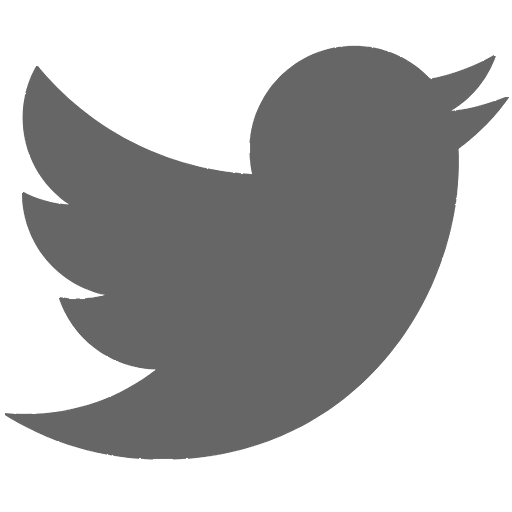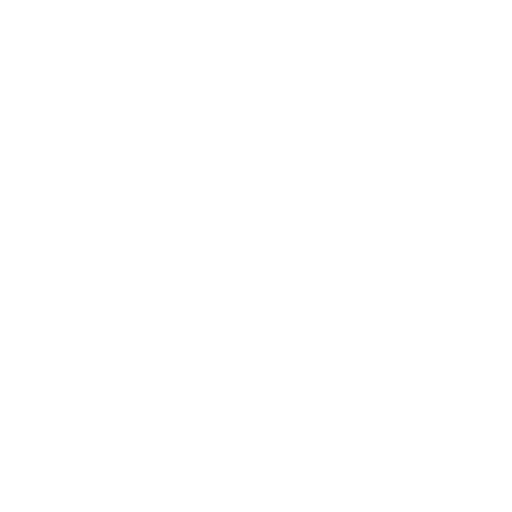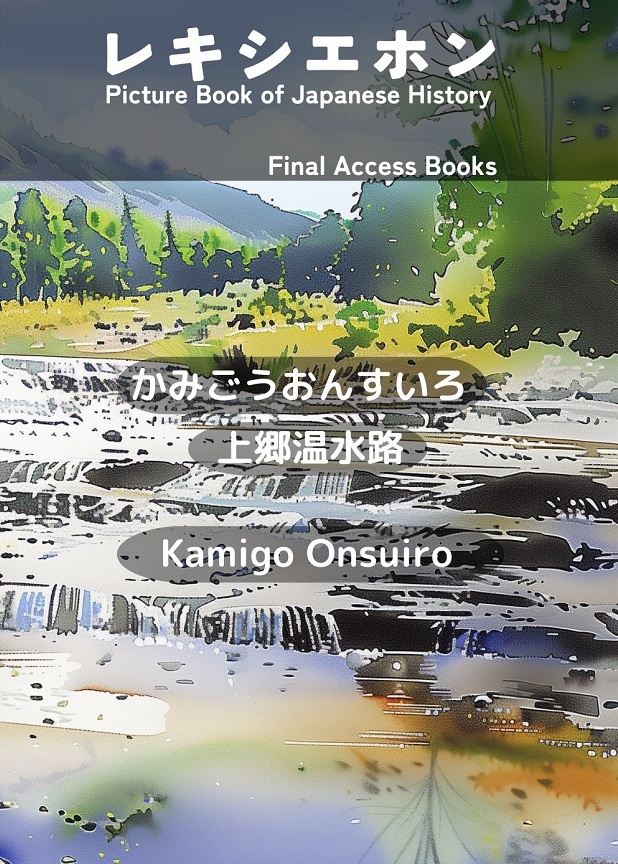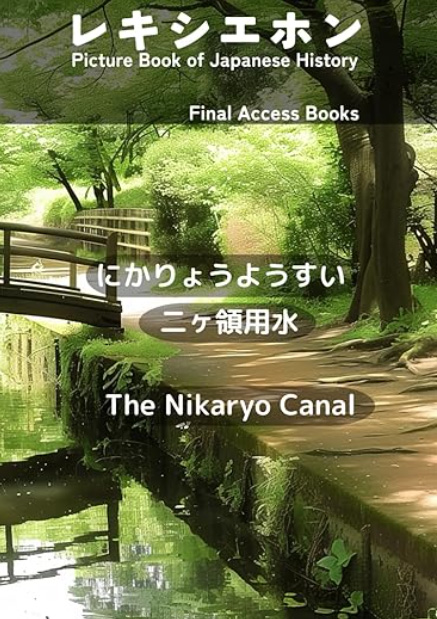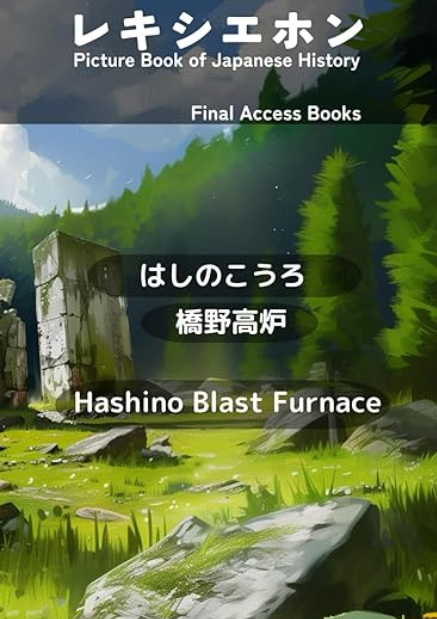二本煙突
- 建物・施設
福岡県田川市の空に、今もなお誇らしげにそびえ立つ二本の煉瓦造りの煙突。これは「旧三井田川鉱業所伊田竪坑第一・第二煙突」の姿であり、地域の人々からは親しみを込めて「二本煙突」と呼ばれています。
この煙突が誕生したのは、日本の近代化が急ピッチで進んでいた1908年のことです。当時、国内最大の出炭量を誇った筑豊炭田の中核を担う三井田川鉱業所が、石炭を掘り出すための動力源であった蒸気ボイラーの排煙設備として建設しました。高さ45.45メートルに及ぶこの巨大な建造物には、21万枚を超える耐火レンガが使用されましたが、その多くが遠くドイツから取り寄せられたものでした。この事実は、日本の産業発展が世界の最新技術と密接に結びついていたことを物語っています。煙突から立ち上る黒い煙は、まさしく日本の産業革命を支えるエネルギーの象徴であり、地域にとっては繁栄の証でした。その姿は民謡「炭坑節」にも「あんまり煙突が高いので さぞやお月さん けむたかろ」と歌われ、人々の暮らしや文化の中に深く根付いていきました。
しかし、エネルギーの主役が石炭から石油へと移る時代の大きなうねりの中で、主力であった三井田川鉱業所は1964年にその長い歴史に幕を下ろします。煙が消えた煙突は、炭都の時代の終わりを静かに見守りました。
閉山後、その跡地は歴史を未来へ継承する場として生まれ変わりました。1983年に田川市石炭・歴史博物館が開館し、2005年には周辺一帯が石炭記念公園として整備され、市民の憩いの場となっています。二本煙突は、2007年に国の登録有形文化財、2018年には国指定史跡「筑豊炭田遺跡群」の重要な一部となり、その歴史的価値が改めて認められました。
日本の近代化という大きな使命を背負い、力強く煙を吐き出し続けた二本煙突。その運営に尽力されたすべての方々へ、心からの敬意を表します。この煙突を見上げる時、私たちの胸にはかつての活気と、そこで生きた人々の力強い息吹がよみがえってくるようです。
(2025年8月改筆)
PHOTO:写真AC