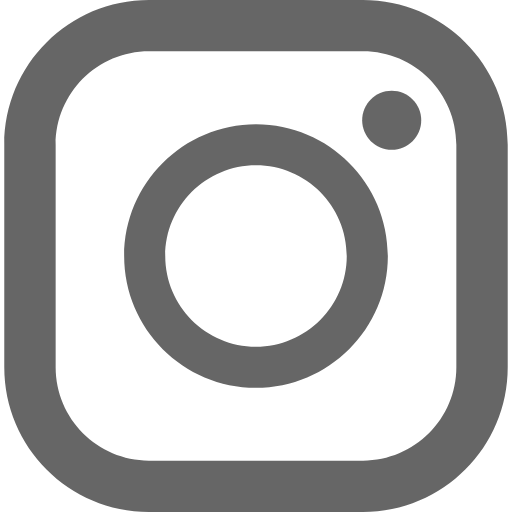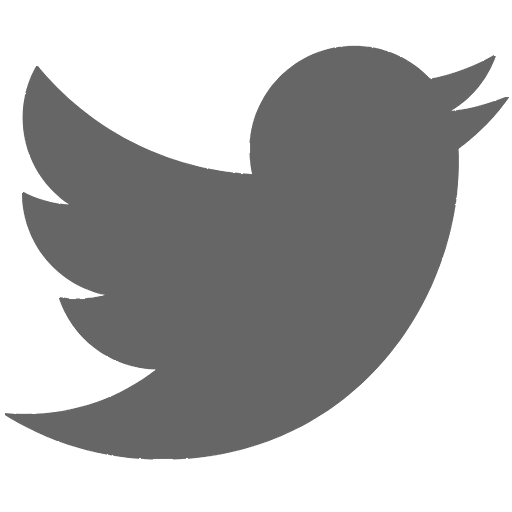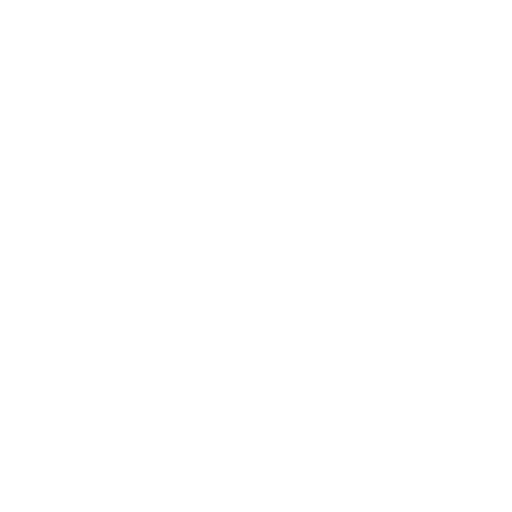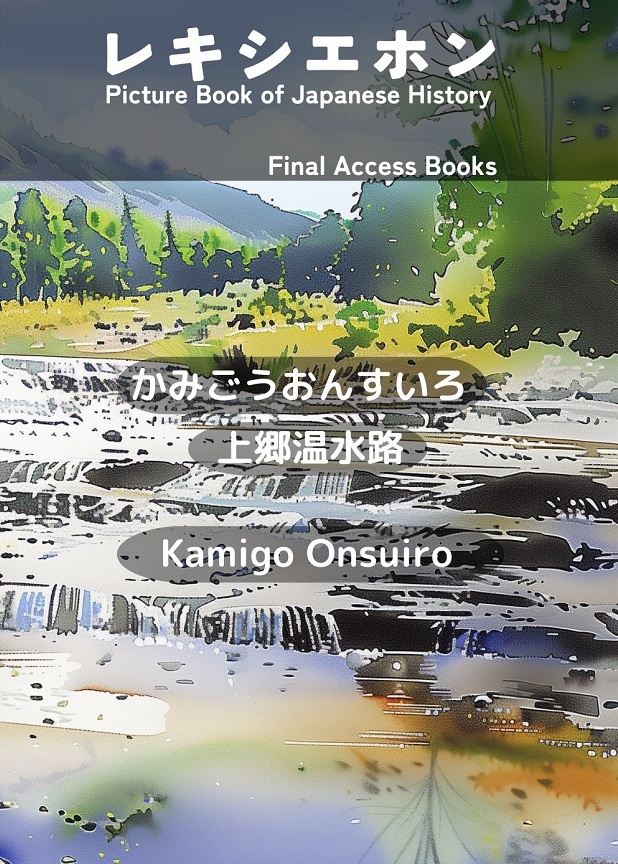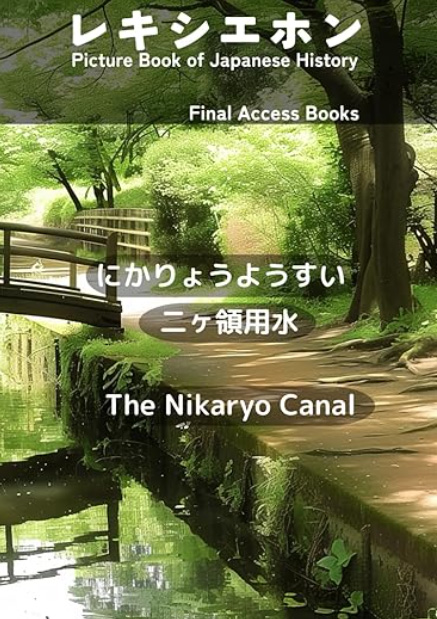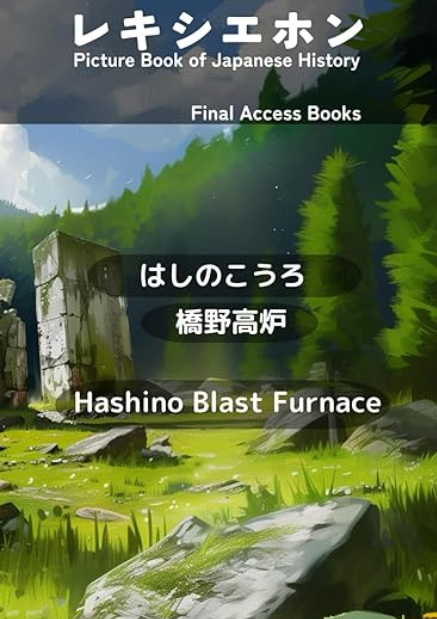北炭赤間炭鉱
- 建物・施設
北炭赤間炭鉱は、北海道炭礦汽船(北炭)による戦略的な事業展開の中で、日本の戦時・戦後復興を支えた重要な炭鉱の一つです。この地域では、明治期の奈江炭山、大正期の赤平坑といった先行事例がありましたが、北炭が本格的な開発に着手したのは1938年または1939年頃でした。これは、当時の国策的な資源確保の必要性と強く連動しています。
戦後の復興期において、石炭需要の増大に伴い、赤間炭鉱は急速に成長しました。最盛期の1951年(昭和26年)頃には従業員数が1,700人を超え、豊里地区(旧赤間2区)は活気あふれる炭鉱コミュニティとして機能しました。また、1955年には末広炭鉱を末広坑として統合するなど、生産効率の維持・向上に努めました。
しかし、1960年代に入るとエネルギー革命が進行し、国内石炭産業は構造的な転換を迫られます。北炭は経営合理化のため「スクラップ・アンド・ビルド」戦略を採用し、相対的に規模の小さかった赤間炭鉱は合理化の対象となりました。末広坑が1969年に先に閉山した後、赤間炭鉱本体も最終的に1973年(昭和48年)に閉山を迎えました。これは、日本経済が石炭依存から脱却する歴史的転換期を象徴する出来事です。
赤間炭鉱の歴史的役割は、地域を超えて公的に評価されています。空知の石炭供給拠点として、北海道の近代化を牽引した「炭鉄港(石炭・港湾・鉄鋼)」の物語を構成する重要な要素であり、この物語は2019年に日本遺産として認定されました。閉山後の2003年には、旧豊里地区に赤間炭鉱碑が建立され、現在も赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設などを通じて、その重厚な歴史が次世代に伝えられています。
この貴重な歴史遺産の保存と運営管理に深く敬意が表されます。歴史ファンの皆様には、かつての日本のエネルギーを支えた人々の熱気と、産業史の足跡を肌で感じるため、ぜひ一度現地を訪問されることを推奨いたします。
(2025年10月改筆)

歴史ロマン溢れる当地ならではの景色と言えそうです。
PHOTO:写真AC