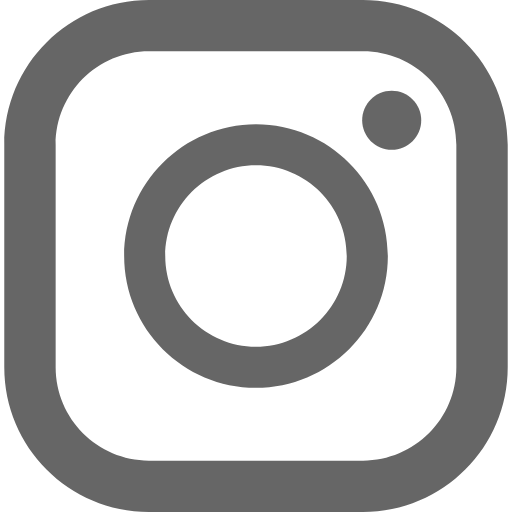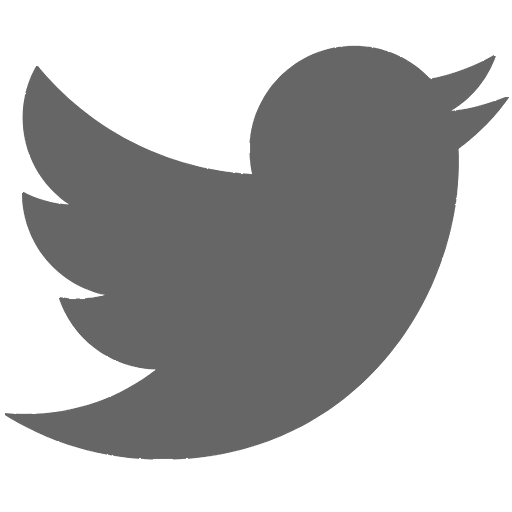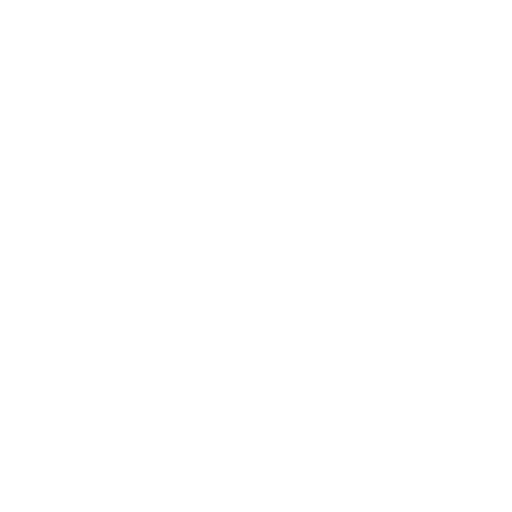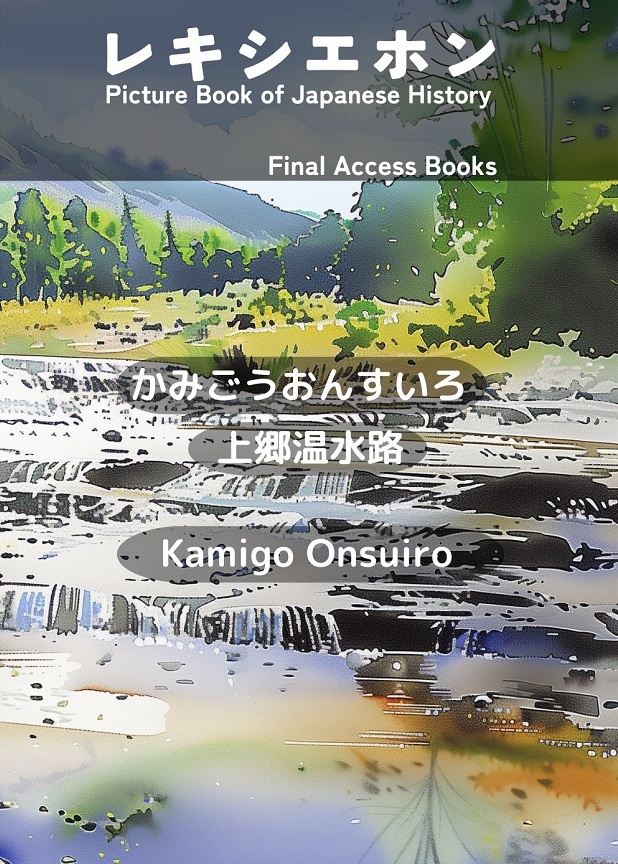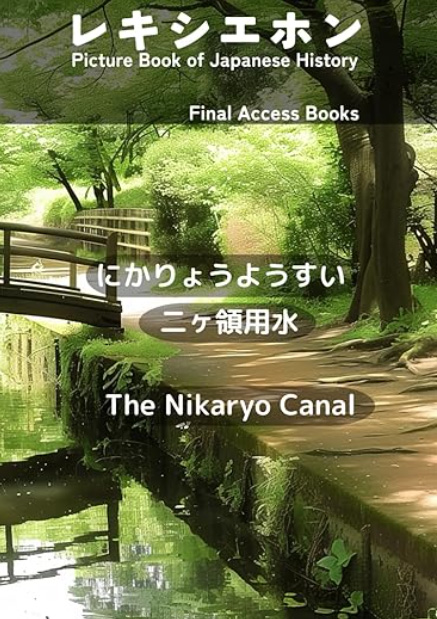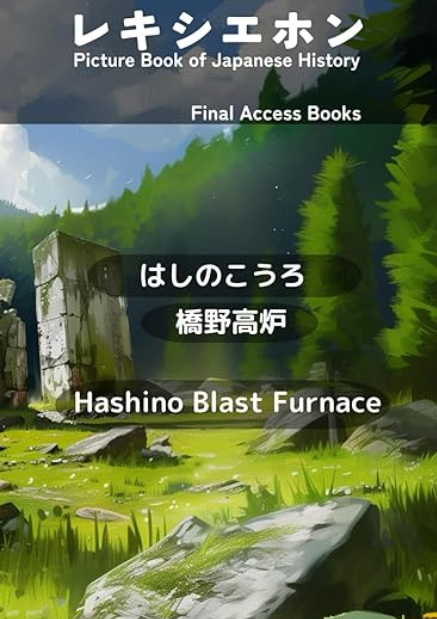国立天文台第一赤道儀室
- 文化・教育施設
国立天文台第一赤道儀室は、日本の近代天文学が新たな一歩を踏み出した象徴的な存在です。20世紀初頭、都市化が進んだ麻布から観測の拠点を移す国家事業の一環として、1921年に三鷹の地に最初に建設された観測施設でした 。三鷹キャンパスに現存する最古の観測用建物であり 、その鉄筋コンクリート造の機能的なドームには、ドイツの名門カール・ツァイス社製の口径20cm屈折望遠鏡が据えられています 。
この施設の最も重要な功績は、1938年から1998年までの60年間にわたって続けられた太陽黒点のスケッチ観測です 。晴れた日には毎日、研究者たちが太陽表面の黒点を丹念に写し取りました。この地道な観測によって蓄積された長期的なデータは、太陽活動の周期性を解明する上で極めて貴重な財産となり、世界の太陽物理学研究に大きく貢献しました。
研究施設としての役目を終えた後、その歴史的・科学的価値が高く評価され、2002年に国の登録有形文化財に指定されました 。現在は「生きている記念碑」として週末を中心に太陽観察会が開催され、来訪者は歴史的な望遠鏡で太陽を直接見ることができます(時期や時間は要確認)。過去の科学研究を追体験できる貴重な機会を提供しています。
この歴史的遺産を丁寧に保存し、科学の魅力を次世代に伝え続ける国立天文台の活動に深く敬意を表します。施設はJR武蔵境駅や京王線調布駅からバスを利用し、「天文台前」で下車するのが便利のようですので、是非一度現地に足を運んでみてはいかがでしょうか。歴史と天体の双方のロマンを感じ取れる貴重な機会になりそうです。
(2025年6月執筆)
PHOTO:写真AC