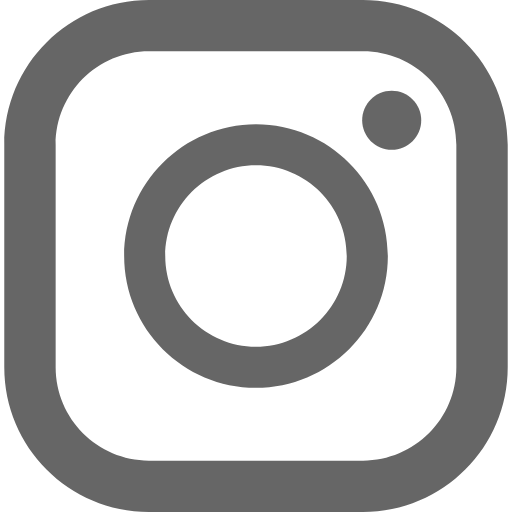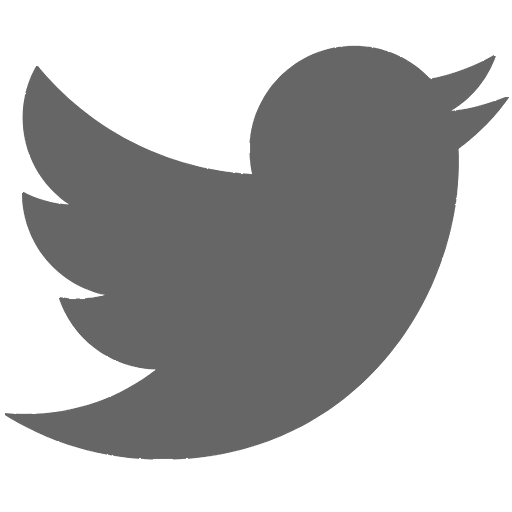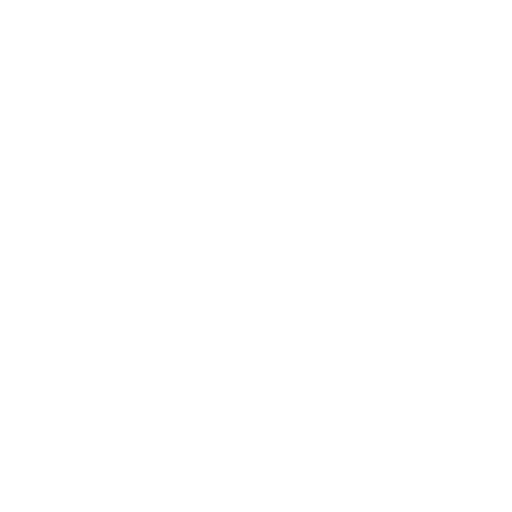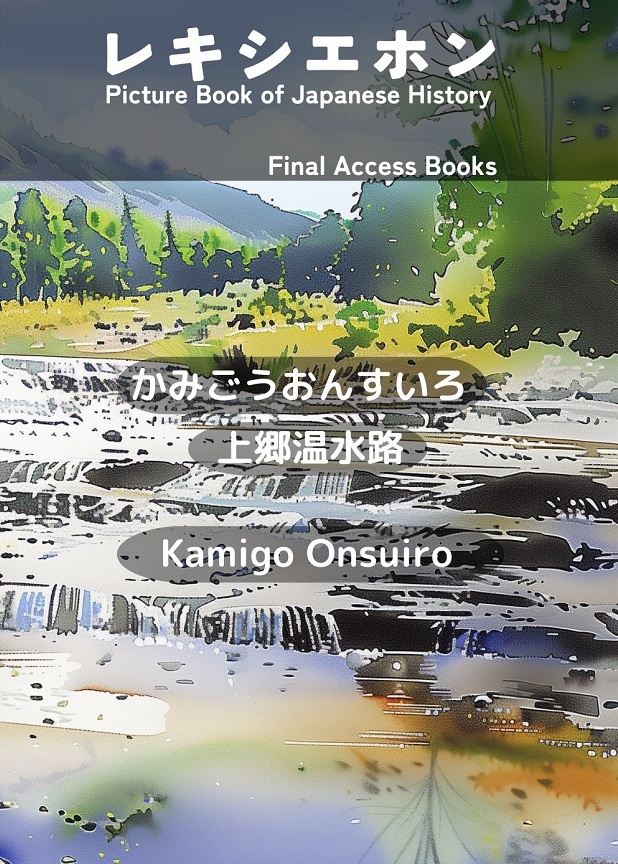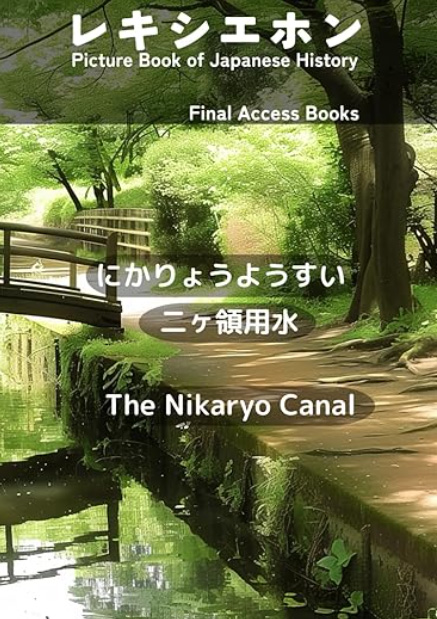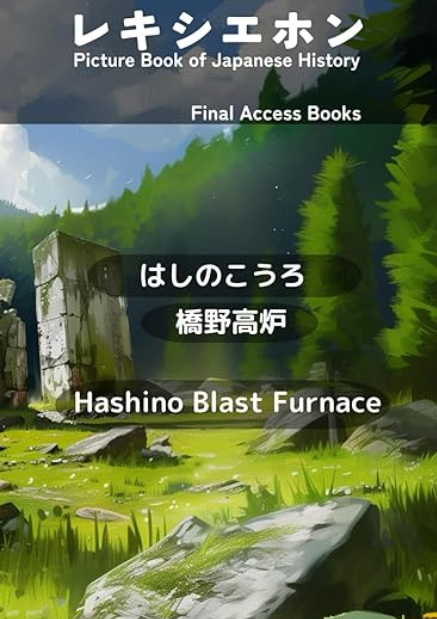松下村塾
- 文化・教育施設
松下村塾の起源は、吉田松陰の叔父である玉木文之進が、1842年に萩の松本村で設立した私塾に遡ります。しかし、当塾が歴史的な輝きを放つのは、松陰自身が主宰者となってからです。
1855年(安政2年)、松陰はアメリカ艦隊への密航に失敗し、萩の野山獄から出た後、生家である杉家の幽囚ノ旧宅に謹慎します。ここで松陰は近隣の門弟たちに講義を始め、翌1856年(安政3年)頃には事実上、松下村塾を開塾しました。1857年(安政4年)には、近くの小屋を修理し8畳一室の塾舎として使用を開始し、1858年(安政5年)には塾生たちの手により10畳半が増築され、現在の二室からなる形となりました。
松陰がこの塾で直接指導にあたったのは、わずか2年半ほどの短期間に過ぎませんでしたが、その教育は身分や年齢を問わず開かれており、兵学・漢学・歴史など多岐にわたり、近代日本の精神的理論的原点となりました。松下村塾からは、明治維新を遂行し、その後の日本の近代化・産業化を牽引した数多くの優秀な人材が輩出されました。特に、伊藤博文や山県有朋といった内閣総理大臣経験者を筆頭に、久坂玄瑞、高杉晋作など、幕末から明治にかけて活躍した偉人たちの揺籃の地として、日本の教育史上においても極めて貴重な歴史遺産と位置づけられています。
塾は1892年(明治25年)に閉鎖されましたが、遺構は塾生や家族の手により大切に保存されました。1907年(明治40年)には、隣接地に松陰神社が創建されます。歴史的価値は公にも認められており、1922年(大正11年)には、松下村塾と幽囚ノ旧宅が国の史跡に指定されました。さらに2015年には、「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の一つとしてユネスコ世界文化遺産に登録され、幕末期における日本の産業化の第一段階を反映する重要な場所として国際的な評価を得ています。現在、松陰神社によって、当時の状態のまま良好に維持管理されており、萩市と連携し、長期的な保存・公開活用計画が推進されています。
往時の姿を今に伝える建造物と、その精神を継承する管理運営主体には、深く敬意が表されます。歴史の大きな転換点における人材育成の熱意を感じるため、歴史ファンの皆様にはぜひ当地を訪れ、松陰先生と若き志士たちの足跡を辿ることを強くお勧めいたします。
(2025年11月執筆)
PHOTO:PIXTA