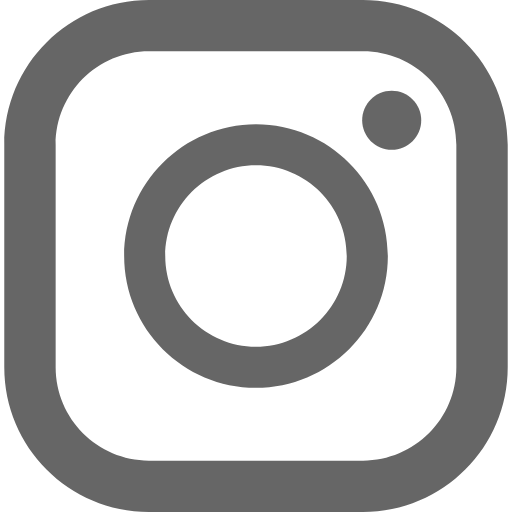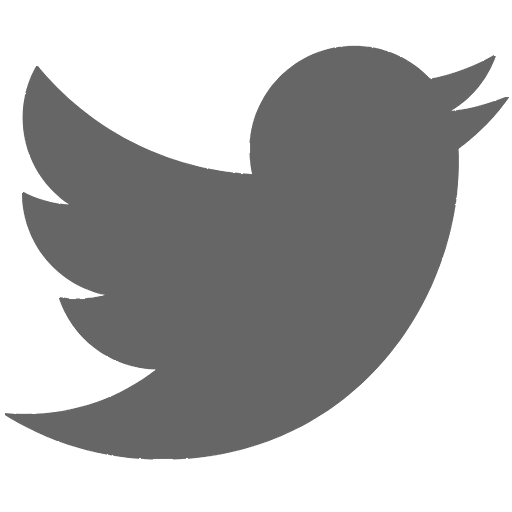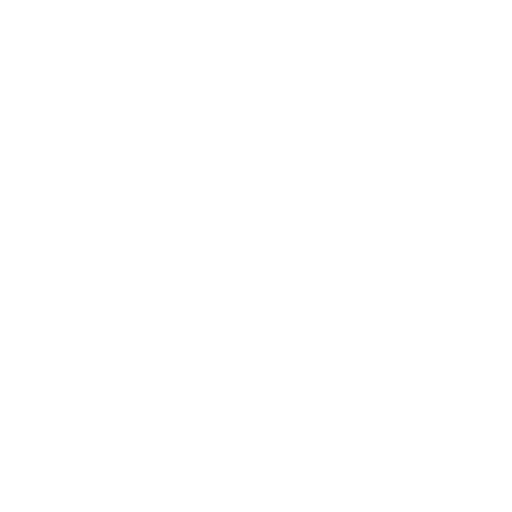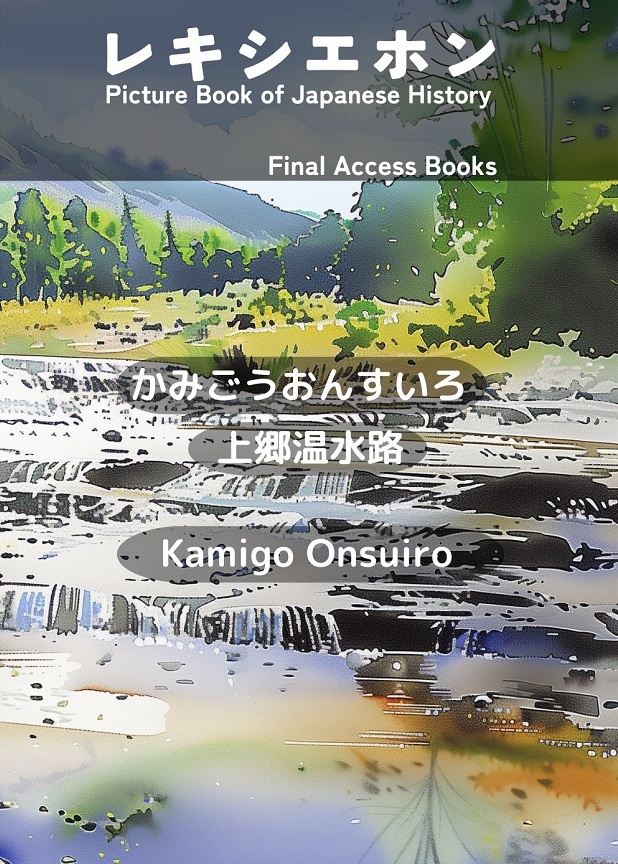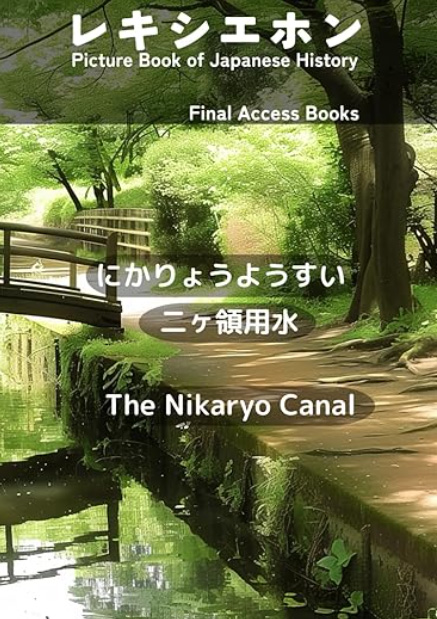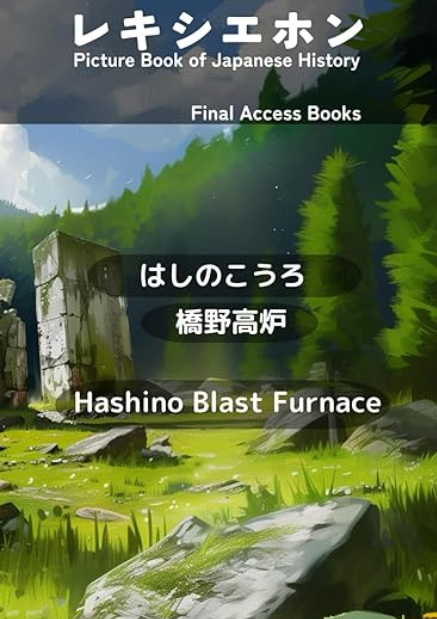【飯田線】 伊那八幡駅舎
- 乗り物
- 建物・施設
長野県飯田市八幡町に位置するJR飯田線伊那八幡駅は、伊那谷の鉄道黎明期からの歴史を物語る、貴重な木造駅舎です。この駅の誕生は、前身となる伊那電気鉄道が路線を延伸していた時代に遡ります。
この駅は、飯田駅から南への延伸が行われた際、その暫定的な終着駅として、1926年12月17日に開設されました。駅舎に貼付された財産票には「昭和元年12月」と記されていますが、これは大正天皇崩御による改元が行われた直後の、わずか七日間しかなかった昭和元年中に公的な資産登録が行われたことを示しており、大正・昭和・平成・令和の四つの時代を見つめてきた駅舎として歴史的な意味合いを持っています。伊那八幡駅舎の最大の魅力は、当時の地方私鉄が地域発展へかけた熱意を伝える、凝った建築意匠にあります。伝統的な木造駅舎とは趣を異にし、洋館風のマンサード屋根に似たファサードが特徴的です。出入口の庇を支える金具のデザインや、壁面のモルタルを掻き落とすといった手の込んだ装飾が随所に見られ、当時の建築技術の高さが偲ばれます。
駅は翌1927年2月5日には毛賀方面へ延伸されたことで途中駅となり、伊那電気鉄道(後の飯田線)の重要な停車場として地域に利用されていきました。その後、1943年8月1日に戦時買収によって国有化され、日本国有鉄道(国鉄)飯田線の一部となります。時代が進むにつれ、1975年に貨物扱いが廃止され、旅客駅となり、1994年には駅員が無配置の無人駅となりましたが、現在に至るまで地域の足として機能し続けています。
しかし、その長きにわたる役目を終える時が迫っています。老朽化対策として、現在の運営管理主であるJR東海は、建て替えの方針を地元に伝えました。この歴史ある駅舎は、具体的な時期は未定ながら解体される方針が示されています。これは、経年劣化した駅舎の耐震化や防火性能向上を進めるためであり、長きにわたり鉄道運行と駅舎の維持管理を担ってこられた現在の運営管理主には、深く敬意が表されます。大正から続く歴史を刻んだこの個性的な木造駅舎を実際に目にすることができる時間は限られています。鉄道の歴史と地域の発展を肌で感じたい歴史ファンの方々には、解体される前にぜひ当地を訪問されることを強く推奨いたします。
(2025年11月執筆)